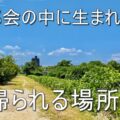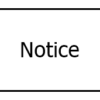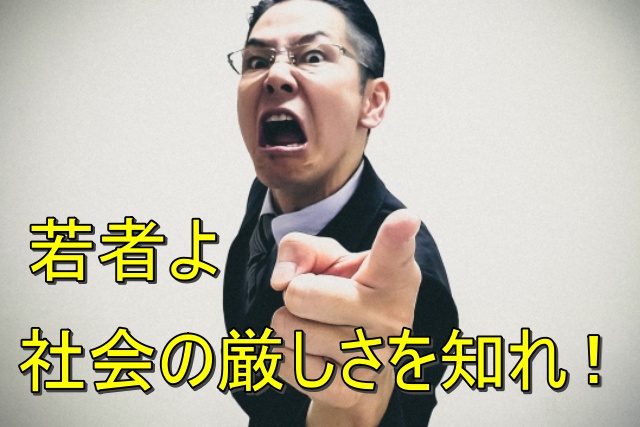
前回の記事では4/1の新年度の挨拶がテーマだった。
新年度初日とはいえ、私のように前日と全く仕事が変わらない人が大半であり、緊張しながらこの日を迎える人といえば、やはり新入社員の人たちであろう。
・入社直後にやることは…

当ブログでも2023年までは5年間に渡り、そんな彼らを励ます言葉をお送りしてきた。
そんな彼らだが、入社式後に早速業務を行う者もいれば、先ずはじっくりと研修を受ける者もいるだろう。
どちらになるかは彼らの選択ではなく、会社の方針で決まるだろうが、「早く先輩と一緒に働きながら仕事を覚えたい」と願う人もいれば、「先ずはじっくりと研修を受けたい」という人もいると思う。
早速この時点でミスマッチが起きるかもしれない(笑)
ちなみに、私は前者の方である。
というのも、私は研修が嫌いだから。
先ずは何と言っても、何時間も座って話を聞かされるのが退屈で、眠気との戦いになる。
それでは「ディスカッション形式だったら、眠くならないから良いのか?」と言われたらそうでもない。
初対面の人に自分から話しかけるなんて出来ないし、意見を求められても、そんなタイムリーな話題は見つからないし、「ディスカッション」と謳いつつ、結局は「自動化やシステム化して効率化と安全性の確保を図りましょう」という建設的な意見ではなく、「自分で判断せずにきちんとルールを守りましょう」、「最後は目視で念入りに確認しましょう」というような結論へ誘導されるお決まりのパターンにウンザリする。
こうした研修も新年度の挨拶と同じく、ほとんどは時間の無駄に終わる。
それだったら、早速現場に放り込まれて、日々の仕事を通して業務を覚える方が、よっぽどためになる。
だが、私が新入社員研修を嫌う一番の理由は、「研修」と称した人権侵害が行われる可能性が高いからである。
・社会人としての基礎は自衛隊で学べる?

今から10年以上前のことだが、当時の私はこの記事で取り上げた地元の工場で働いていた。
ある日の休憩中、事務所に電話がかかってきた。
職場への電話は常に社員が取っていたが、その時は社員が不在だったため、65歳のパート職員である男性が電話を取った。
その電話は本部からの連絡で、彼に要件を伝えて、後ほど社員が折り返すことになった。
翌日の休憩中にそのことが話題になり、社員が全くやり方を教えていないにもかかわらず、彼の電話対応が完璧だったことを褒めていた。
すると彼はこんなことを言った。
「俺は昔、自衛隊に居たからね。そういうことは厳しく指導されていたよ(笑)」
それを聞いた社員のB(仮名)は深く頷きながら、こう返した。
そこから、彼は自身が受けた研修の話をした。
「自衛隊は上官が鬼のようにしごいてくる」という事前のイメージ通り、それは過酷な研修だったという。
たとえば、朝礼で指導役の講義中に私語が聞こえたとして、全員が連帯責任で腕立て伏せをさせられたり、「ベッドメイキングが出来ていない!!」と言われてベッドを窓から放り出されたこともあったとのこと。
ちなみに、彼の最初の就職先は食品工場だったそうだが、自衛隊で業務と密接に関わりそうな調理や食品衛生についての研修を受けたわけではなかった。
彼は私より5歳年上で高卒で就職したようなので、私がその話を聞いた時点ですでにおよそ10年前の話となっていった。
しかし、当時の私は決してそれが古い時代の習わしという牧歌的な態度を取ることが出来なかった。
なぜなら、その頃ですら、新入社員を自衛隊体験入隊で鍛えるという噂は聞かれていたからである。
2025年3月現在では非公開となっているが、当時の私が傾倒していた脱社畜ブログでも、「ゆとり世代」と呼ばれる甘ったれた新入社員を社会人として通用出来る最適な方法として自衛隊研修を取り入れる企業を批判的に紹介していた。
私も彼の意見と同じく自衛隊体験入隊、または自衛隊形式を取り入れたという研修には否定的な考えだった。
・欲しいのは文句を言わない兵隊

こうした研修を推し進める者は、社会人として必要な規律、チームワーク、忍耐力、責任感を養うなどと豪語している。
【主催者JTBをご紹介】体験型人材育成プログラム「The 社会人道」:研修会社インソース~講師派遣研修/公開講座の研修
そんな綺麗ごとを言っているけどさ…
要するに、どんなに長時間働かせても決して壊れることがない体力があって、理不尽な要求にも文句言わずに従い、労働基準法なんてものを一切主張しない従順な兵隊が欲しいんでしょう?
元自衛官で、かつて私がコンビニでバイトをしていた時の相棒だった軍曹(仮名)のように。
彼はオーナーや店長(オーナーの息子)の従順な犬で、残業や急なシフトの代役など店側の都合による勤務形態の変更を打診された時も「はい!! 喜んで!!」と笑顔で服従し、集めたところで何の報酬も出ないポイントカード加入の呼びかけも積極に行い、加入してくれる者がいれば、「これでオーナーに喜んでもらえる!!」と言いながら、本人がいない所でも尻尾を振っていた。
副店長であるババア(仮名)に対しても、内心は腹に据えかねていたようだが、我々の勤務時間帯の業務の不手際により、説教されたり、業務改善を要求された時は自身に原因がなくても、一切の弁解をせずに「申し訳ありません!!」と謝りながらペコペコと頭を下げていた。
その一方で、数日で退職する人のことを「根性がない」と陰口を叩き、商品の破損やレジの違算が発生すれば、要求される前から自腹で埋め合わせを行うなど骨の髄までオーナーに従順だった。
こうした姿こそが、「新入社員を自衛隊に入れて鍛えたい!!」と言っている者の理想像なのだろう。
本音としては、自分にだけ従順な兵隊を求めながら、口では「自律」だの「チームワーク」など正反対で嘘八百の言葉を並べ立てる欺瞞に満ちた姿には吐き気を催さずにはいられない。
・ある意味では自衛隊よりつらい

とはいうものの、最近まで学生で、社会の荒波に揉まれていないであろう若者に、「社会の厳しさやお金を稼ぐことの大変さを知ってほしい」と願う気持ちは、私も中高年の端くれとしてはよく分かっているつもりである。
そんな人たちにぜひとも導入を検討して頂きたいお勧めの研修がある。
それは鉄道会社で駅員として勤務することである。
特に新宿、渋谷、池袋など都市部の中心駅で。
私は日々電車で通勤しており、駅で働く職員の姿は何気ない日常の光景となっているが、改めて注意して見ると、その仕事はとても大変のように思える。
鉄道に限らず、輸送機関にとって最も大切なことは安全である。
私のような事務職は数字の1つや2つ間違えたところで大した問題ではないが、鉄道ではほんの少し気の緩みから生じるミスでも重大事故に繋がりかねないので、常に緊張感を保たなくてはならない。
そして、鉄道は他の交通機関よりも定時性に優れているが、裏を返せば働く人がそれだけ時間厳守が求められているため、分ではなく秒単位の遅れも問題になることさえある。
「時間に厳しい」と言われがちな日本社会の中でも、一段と時間管理を求められることだろう。
また、車椅子を利用する乗客の介助や、乗務員、指令室など円滑にコミュニケーションを取りながらチームワークを大切にしなくてはならない。
しかも、勤務時間が不規則で、土日出勤はおろか、早朝や深夜の勤務も行わないといけない。
しかし、駅員研修で最も育まれるであろうものは、なんといっても忍耐力である。
都心部で毎日電車通勤をしていると、ただでさえ人混みが激しい上に、あまりにもマナーやルールを守らない人間が多くて、毎日が修羅場だ。
あれだけ毎日至る所で繰り返し「止めろ!!」と言われているにもかかわらず、歩きスマホ、ワイヤレスイヤホンを耳に入れたままでの電車の乗り降り、ホームドアへの寄りかかり、エスカレーターの駆け下り、駆け上がり、駆け込み乗車、押し込み乗車など不届き者たちがやりたい放題である。
平時でさえ、このような烏合の衆を相手にせねばならず、電車の遅延や運転見合わせなど発生しようものなら、駅員を罵倒したり、混雑で殺気立った乗客同士による押し合い、挙句は喧嘩まで起きる。
その他にも、痴漢や盗撮などの性犯罪、恥部を露出したり、トイレではない場所で排泄する酔っ払いなど警察が対応すべき事案も発生する。
もしかしたら、「新入社員を自衛隊で鍛えたい!!」などとご立派なことを宣う人が、そのようなクレーマーだったり、犯罪者だったりするのかもしれない。
テレビやネットでは「世界が尊敬する素晴らしい日本人のマナー!!」といった日本礼賛を度々目にするが、鉄道の駅はインターネットの匿名掲示板並みに人間のどす黒い本性が現れる場となっており、そんな言説は大嘘であることがすぐに分かる。
乗客としてたかだか1日に数十分利用して、夜は年に数回しか外出しない私でさえこんな思いをするのだから、駅員の方々は、遥かに醜い光景に遭遇していることは間違いない。
駅員として働く上では、毎日このようなモンスターの相手をしなければならない。
自身や社会の安全を脅かすならず者を外敵として駆逐することが許されない分、もしかしたら、自衛隊よりもつらいかもしれない。
「奴ら一発ぶん殴ることが出来たら、どんなに胸がスッとするだろうか…」と思うのは、決してサイコパス思考だからではなく、人間としての自然感情である。
こうした駅員としての仕事で研修を受けたら、仕事への緊張感、規律と時間の厳守、和の尊重、体調管理、社会の理不尽さ、週末休みで固定時間勤務のありがたみを学ぶことは他の職業でも大いに役に立つに違いない。
また、お下劣な愛国ポルノ感染予防にも役立つこと請負である。
というわけで、鉄道会社の皆様には、コロナの影響により低下した鉄道事業の収益を少しでも補填するためにも、新社会人向けの駅員体験研修事業の創設をご検討頂きたい。