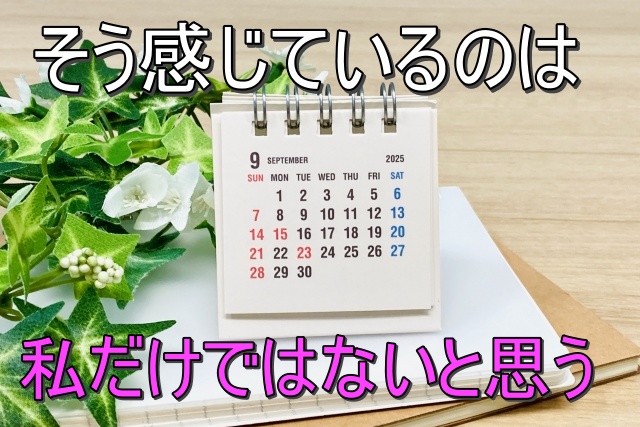
今日は9月21日。
明後日の23日は「秋分の日」である。
今年はこの日について、どうしてもモヤモヤすることがある。
・秋分の日の理念とは?

秋分の日とは、日本の国民の祝日の一つであり、カレンダーにも赤く印刷されているので誰もが目にしているはずだが、その意味や趣旨を他人に説明できる人は決して多くないと思う。
かくいう私も、この記事を書くまで「秋の入口」くらいの認識だった。
祝日法によれば、この日の趣旨は「祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ日」とされている。
つまり、単なる季節の節目ではなく、先祖供養や家族のつながりを意識することが目的のよう。
また、天文学的にみれば、秋分の日は「昼と夜の長さがほぼ等しくなる日」である。
太陽が真東から昇り、真西に沈むため、昼と夜が均衡する。
この日を境に北半球では日照時間が短くなり、季節は本格的な秋へと進んでいく。
二十四節気の「秋分」に当たり、自然のリズムを実感できる瞬間でもある。
さらに、仏教や日本の民間信仰では、秋分の日を中心とした前後3日間を合わせて「秋のお彼岸」と呼ぶ。
お彼岸は春分と秋分の年2回あり、いずれも昼夜の長さが等しくなるこの日に、あの世とこの世が最も近づくと考えられてきた。(厳密に言えば、「必ずしも『等しくなる』というわけではない」らしいが…)
春分の日・秋分の日には、昼と夜の長さは同じになるの? | 国立天文台(NAOJ)
そのため、多くの家庭で墓参りをしたり、先祖に供物をささげたりする風習が続いているとのこと。
このように秋分の日には「自然を敬う」、「先祖をしのぶ」という二重の意味が込められている。
・ハッピーマンデーでもないのに、年によって祝日となる日が違う
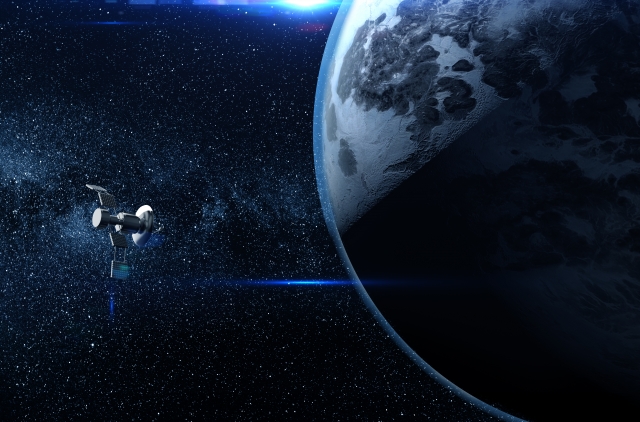
祝日の多くは、毎年同じ日付に設定されている。
元日が1月1日、建国記念の日が2月11日、天皇誕生日が2月23日など、カレンダーを見れば動かない日がほとんどだ。
ところが春分の日と秋分の日は「ハッピーマンデー」の適用外であるにもかかわらず、年によって9月22日、または23日になったり、春分の日も3月20日や21日に揺れ動くことがある。
なぜこうした不安定さが生じるのか。
その理由とは、「これらの祝日は天文学的な基準に基づいているから」らしい。
地球が太陽の周りを1周するのに要する時間は、365日ちょうどではなく、約365.24219日である。
そのため、毎年少しずつズレが生じ、4年に1度の閏年で調整しても完全に一致するわけではない。
結果として、春分や秋分は年ごとに微妙に前後し、祝日の日付もそれに合わせて変動する。
春分の日はなぜ年によって違うの? | 国立天文台(NAOJ)
祝日法でも「春分日」「秋分日」とだけ定義され、具体的な日付は条文に書かれていない。
翌年の春分・秋分の日がいつになるのかは、国立天文台の計算によって決まり、官報で告示されて初めて公式の祝日として確定する仕組みになっている。
何年後かの春分の日・秋分の日はわかるの? | 国立天文台(NAOJ)
他の祝日が政治的な理由や歴史的な記念日に基づくのに対し、春分と秋分は「自然現象に忠実に設定される祝日」という点で特殊な存在である。
だからこそ、毎年必ずしも同じ日にならず、ハッピーマンデー制度の対象にもならない。
・この日こそハッピーマンデーにすべきではないか?

ここまで秋分の日の趣旨や変動の理由を説明してきた。
己の無知と恥を晒すようで心苦しいのだが、私は30代だが、ほんの数年前まで、「春分の日=3/21」、「秋分の日=9/23」だと思っており、春分の日が3/20、秋分の日が9/22となる年があることなど全く意識していなかった。
だが、私は疑問に思う。
「春分の日や秋分の日はハッピーマンデーを適用外にしたり、毎年該当日が不確定となる不便さを強いてでも、理念を遵守すべきものなのか?」
まず、秋分の日を「昼と夜の長さが等しい日」として強く意識している人はどのくらいいるだろうか。
同じ自然現象でも夏至や冬至は、テレビのニュースや天気予報で取り上げられることが多く、「一年で最も昼が長い(短い)日」といった意識を持つ人も少なくないだろうが、私は「今日は秋分の日だから、昼夜の長さが等しくなる日ですね!」と言っている人など見たことがないのだが…
さらに、スーパーで働いた経験があり、今でも客としてよく訪れている経験からも言えるが、秋分の日のお彼岸を特別に祝うための商品セットなど見かけたことがない。
お正月ならおせち料理、ひな祭りならちらし寿司や雛あられ、お盆にはお供えセットといった具合に、季節の行事に合わせた商品展開は数多く存在する。
しかし、秋分の日に関しては、そうした商業的な盛り上がりは皆無に等しい。
多くの人は、春分の日は「学生にとっては春休みの入口で、勤め人にとっては年度末のラストスパートのスイッチを入れるきっかけとなる日」、秋分の日は「敬老の日のついで」程度の意識しか持っておらず、「(祝日法の趣旨にある)祖先へのうやまいや、天文学的な理由など、どうでもいい」と考えているのでは、というのが私の仮説。
そうであるならば、日付を自然現象に忠実に合わせるよりも、むしろ現代人の生活に即した形で運用すべきではないか?
たとえば、ハッピーマンデー制度を適用し、9月の第3か4月曜日を秋分の日とすれば、3連休を安定的に確保でき、仕事や学校の都合に合わせやすくなる。
今年は9/22が月曜日であり、年によってはこの日が秋分の日となることに何の違和感もなく、3連休を逃したからこそ、余計にそう思う。
お彼岸との関係がずれるという反論もあるだろうが、実際にはお墓参りも家族の都合で週末に行くケースも多いと思う。
必ずしも「中日」に行う必要があるわけではないのだから、大きな支障はないのではないか。
「自然現象に忠実」という建前は確かに美しい。
だが、その建前を守るために、国民が休暇を有効に活用できないのであれば本末転倒だ。
秋分の日が毎年9月22日や23日を行き来するせいで、せっかくの休みが飛び石連休になったり、場合によってはただの一日休みになってしまうこともある。
それよりは、安定した三連休を実現するほうが、国民にとっては実際的なメリットが大きいだろう。
秋分の日を「自然を敬う日」とする精神自体を否定するつもりはない。
ただ、その趣旨が国民生活に深く根付いていない現状を考えると、むしろ形式にとらわれず柔軟に運用したほうが祝日の価値は高まるのではないか、と私は思っている。









