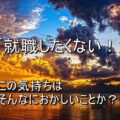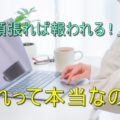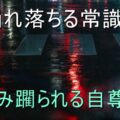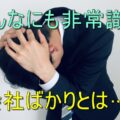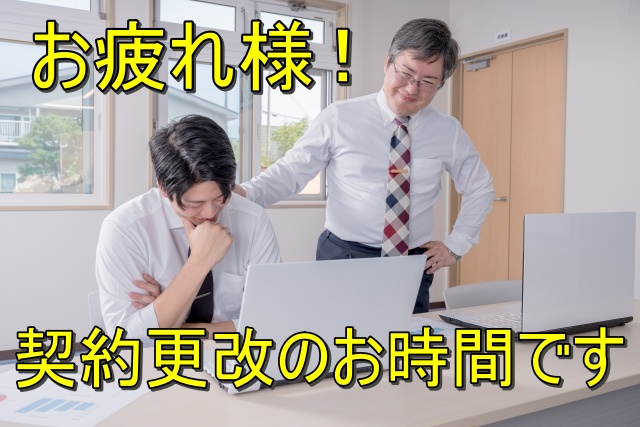
今年のプロ野球も日本シリーズが終了した。
日本シリーズ終了後に解禁となることと言えば、FA(フリーエージェント)権の宣言である。
多くの読者にとっては改めて解説する必要はないと思うが、プロ野球選手はプロ入りする際に所属する球団を自由に選べず、全球団一斉に行われるドラフト会議で指名された球団としか契約できない。
球団から自由契約を宣告されてクビにならない限り、選手の意思で他の球団に自由に移籍するためには、一軍登録日数が一定期間に達することで取得するFA権を行使しなければならない。
つまり、働き盛りの年齢で球団からも必要とされている大物選手の移籍となれば、必然的にFA移籍となる。
・日本とアメリカのFA制度の違い

日本プロ野球(NPB)の制度の多くはアメリカ(MLB)から輸入されたものであり、FA制度もアメリカ由来となっている。
しかし、現在のFA制度は必ずしも似ているとは言えない。
日本(NPB)のFAは、入団の経緯や移籍先が国内か海外かによって異なるが、一軍登録日数が通算7~9年で取得できる。
一方のMLBはメジャー在籍6年で取得となる。
NPBの取得日数については、制度導入から徐々に短縮され、選手会も度々取得日数の短縮を要求しているため、今後はさらに短くなり、MLBとの差が縮まるかもしれない。
だが、根本的に異なる点は、権利取得後の流れである。
日本の場合、FA権を行使については本人の宣言が必要であり、行使しなければ、球団はその選手を引き続き保有でき、選手のFA権も持ち越しとなり、翌年以降は自由に宣言することができる。
これに比べて、メジャーでは、6年以上在籍すると選手の意思に関わらず、自動的にFAとなり、シーズン終了後の5日間は元球団のみ交渉可能となるが、その後はFA市場で全球団と自由交渉することになる。
要するに、すべての契約が一度リセットされるのだ。
日本の場合は選手が自主的に宣言しなければならないため、権利の行使をすれば「裏切り者」、「金目当て」、「チーム愛がない」などと非難されることもあるため、制度上は問題なくても、移籍までのハードルが非常に高い。
対して、メジャーの場合は自動でFA扱いとなるため、痴情のもつれのような泥沼に発展することなく、移籍するにせよ、残留するにせよ、ドライに契約交渉することが出来て、年俸アップや待遇改善にも繋がりやすく、移籍も活発化する。
とはいえ、この制度は良いことだらけというわけではなく、選手側にも大きなリスクがある。
FA権を取得するタイミングで球団側に再契約の意思がなく、他の球団とも契約がまとまらなければ、所属球団なしの状態となり、場合によってはそのまま引退となってしまう可能性もあるのだ。
・自由の裏のリスク

日本では、長年チームに貢献した選手が戦力外通告を受けて退団となった場合は、球団が「功労者に対する非情のリストラだ!!」と批判され、選手に同情の声が集まることが少なくない。
一方、メジャー式の自動FAでは、FA取得のタイミングで球団側が「これ幸い」と契約延長を行わなければ、そうした話題にすらならず、人知れず静かに球界から姿を消してしまう。
もちろん、球団には高年俸のベテラン選手を放出する際の汚れ仕事も発生しない。
今から10年前の2015年オフ、広島東洋カープに所属していた木村昇吾選手がFA権を行使した。
FA宣言をしたものの、公示から1ヶ月以上経ってもどの球団からも声がかからず、元の所属球団も再契約の意思がなく、埼玉西武ライオンズから入団テストのオファーがあるまでは、「このまま引退するのでは?」と心配されていた。
彼は自ら権利の行使を宣言したわけだが、MLB方式の自動FAに移行したら、本人の意思とは無関係に同様のケースが大量に発生するだろう。
この構造を冷静に見ると、MLBのFA制度は「選手保護」というよりも「市場原理の徹底」である。
年齢や成績によっては、あっさり切り捨てられるリスクを常に抱えている。
「日本もFA制度はMLB方式にすべきだ」と主張する声は根強い。
「宣言の必要がなくなるから、選手の心理的ハードルが下がる」
「移籍が増えて球界が活性化する」
「もっと市場原理を導入した方が、選手が報われるようになる」
といった、分かりやすい理想論である。
確かに、スター選手が自由に動けば話題性は増すし、年功序列的な年俸構造も是正されるかもしれない。
しかし、現実にはそれほど甘くなく、MLB式の自動FA制度導入を主張している人たちは、選手が自動的に所属球団を失ってしまうことも理解して賛成しているのだろうか?
もしかしたら、「年功序列や温情で不要なベテランを放出できない日本球界の悪い点を廃止できる」と喜んで賛成しているのかもしれない。
・派遣社員の契約更新は自動FAと似ている

さて、メジャーリーグの自動FAをしているとこんなことを感じた。
なんだか、派遣社員の契約更新制度と非常によく似ているな。
日本で派遣社員として働く時は数年間に渡る長期前提の案件でも、たいていは3ヶ月毎に契約更新を繰り返す。
更新のタイミングで、派遣会社が派遣先の担当者と派遣社員の間に立って、双方の合意が行われて、どちらかが「もう更新しない」と言えば、それで雇用関係は終了。
だが、それは一方的な「解雇」ではなく、あくまで「契約満了」であり、「裏切り者」、「非情なリストラ」といった感情論にはなりにくい。
労使双方にとって、穏やかに関係を終える制度的装置として機能している。
お互いに契約延長を希望する場合であっても、契約期間が切れる場合では、自動延長とならず、もう一度契約書を作り直さないといけない。
この契約更新のタイミングで、雇用を継続する上でお互いの懸念点について堂々と話し合うことが出来る。
たとえば、パフォーマンスが給与に見合っておらず、一向に改善も見込めない場合の最後通告や、職場環境、給与、職務内容の不満など、更新のタイミングがなければお互いに相談し難かったり、伝えても「なあなあ」で済まされてしまうことも、正面から向き合って交渉せざるを得ない。
長期であっても契約更新が繰り返されることには、「労働者は3ヶ月毎に『今度も無事に契約更新されるだろうか…😰』という不安に苛まれる」といった視点ばかりが強調されるが、労働者側にとっても強力な交渉チャンスになる。
私自身、派遣先の人員配置や部署体制の変更という派遣先都合で契約終了となったこともあるが、逆に人手不足や部署内に同等のITスキルを持った人がいない状況で、職務内容を理由に契約更新を渋ったところ、時給200円アップ、クレーム対応から外れる、繁忙期でも残業免除などの好条件を勝ち取ったことも何度かある。(自慢に聞こえたらゴメンね♡)
こうした経験から、特に退職を考えない場合でも、日常業務の中で「お、これは今度の契約交渉で使えるかも!」と面白い発見があったり、職場における自分の評価を改めて確認できるなど、契約更新が楽しい行事となった。
要するに、派遣社員の契約更新制度は、自動FAと同じで短期契約はリスクと引き換えに、交渉権を最大化する仕組みなのだ。
・正社員も年功序列なんて廃止して契約交渉したら?

自身の経験を通して私は思う。
いっそ、正社員も年功序列や終身雇用、全従業員一律の扶養手当や住宅手当、人事考課によるボーナス支給なんて止めにして、契約期間を区切り、契約更新時には個々の職務内容・成果・希望を踏まえて、給与や手当を再交渉するようにしたらどうか?
もし交渉がまとまらなければ「今までありがとうございました」ということで契約終了。
「正社員は非正規と違って、たくさんの競争を勝ち抜いて入社した優秀な人たちなんだから、それに相応しい待遇を用意されているだけだ!!」
「正社員は勤続年数が長くて、その間にたくさんの経験とスキルによって得た地位を奪うな!!」
と言って大反対する人もいるだろうが、とんでもない。
そんな彼らには優秀だからこそ、年功序列や全従業員一律の手当などの甘ったるい労働条件ではなく、正当な評価と報酬で報われて欲しい。
そのためには、長期雇用であっても、契約更新のタイミングで随時交渉して欲しい。
「ボーナスの金額が低すぎるので、契約更新は一旦保留させて頂きます!!」
「今まで新卒3年以内だから我慢していたけど、一流大学を出ている私にその程度の年収しか出せないなら他へ行きます!!」
「私はこれまで総合職として15年の経験を積んで、これから10年がキャリアのピークとなるでしょう。というわけで、賞与を除く最低保証年収1,500万円の10年契約、管理職のポスト保証、地方支社への異動拒否権付与、3時のおやつを無料支給、子どもの大学の学費を半額負担が契約更新の条件です」
非大卒で派遣社員の私ですら、更新のタイミングで人手不足やITスキルで待遇を改善できたのだから、スキル、経験、実力、学歴とすべて勝る彼らであれば、もっとお金を引き出せそうな武器をお持ちだろうから、それを盾にして庶民に羨ましがられる大型契約を勝ち取って欲しい。
もちろん、完全な自由競争にすれば企業側が一方的に有利になる危険もある。
そのため、労働者保護の観点から「減額制限」を設けるのも一案だ。
たとえば、前回の契約から25%以上の減額は不可とするルール。
根拠は単純で、プロ野球の「年俸更改」における減額制限となっており、「取りあえずこれくらいなら、翌年に税金を引かれた上でも生活は成り立つだろう」と思うから。
こうした最低限の安全装置があれば、恐怖も過度に和らぐだろう。
これなら企業も「成果に応じた報酬体系」を築けるし、労働者も「交渉によって待遇を引き上げる余地」を確保できる。
全面的に信じているわけではないが、日本人の気質として、「遠慮しがちで、声を上げて正当な権利を主張しづらい」と言われることがある。
プロ野球選手がFA権の行使を躊躇う理由もまさにそれであろう。
だからこそ、そんな謙虚で奥ゆかしい人たちでも、自分の働きぶりを正当に評価してもらえるように、契約期間が一旦終了したら、これまでの頑張りや今後の待遇について、ゼロベースで交渉してほしい。
自分の主張がすべて受け入れらず妥協案で締結したとしても、お互いに腹を割って話し合えば、
「こんなに頑張っているのに会社は自分のことを分かってくれない!!」
「あいつは上司にゴマをすって評価されているだけだ!!」
という漠然とした不満も解消されるだろう。
日本ではここ30年、賃金が上がらないと言われている一方で、「物価や社会保険料が高騰して生活が困る!!」と憤りの声を上げる者も少なくない。
「育休や産休の導入で仕事をしない奴ばかり優遇して、懸命に会社のために働く人の待遇を一向に改善しない!!」といった声も聞かれる。
それは決して間違いではないと思う。
こうした状況を打破するためには、政治家の政策や労働組合の活動に期待するよりも、各々がこうした交渉を通して、自らの権利を獲得していく方がはるかに手っ取り早い。
もちろん、この考えに真っ向から反対する人もいるはずだ。
「ローンが組めず、家族を養えないから、人生設計ができなくなる…」
「賃上げも待遇改善もどうでも良いから、とにかくクビになって路頭に迷うことだけは避けたい…」
たとえばこういう人たちとか。
JR東労組が「敗北宣言」 スト計画の顛末…3万人脱退、立て直し前途多難(1/4ページ) – 産経ニュース
確かに、その懸念は理解できる。
だが、日本のプロ野球も「移籍の活性化や不要なベテラン選手を排して若手にチャンスを与えるために自動FAの導入を!」と主張している人は、きっと喜んで賛成してくれるだろう。
「他人に雇用の流動化」や「組織の健全な新陳代謝」を望むのであれば、「先ずはご自身の環境をそのようにしてください」と言う他ない。