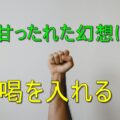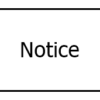先日、同僚が風邪を引いて仕事を休んだ。
ほとんどの人は彼を心配していたが、一人だけは全く別の反応を示した。
「いい歳した大人が、そんなことで休むなよ!!」
「俺は風邪なんかで休んだことはないぞ!!」
それを聞いた私は昔の職場のことを思い出した。
・飛んで火に入る夏の虫
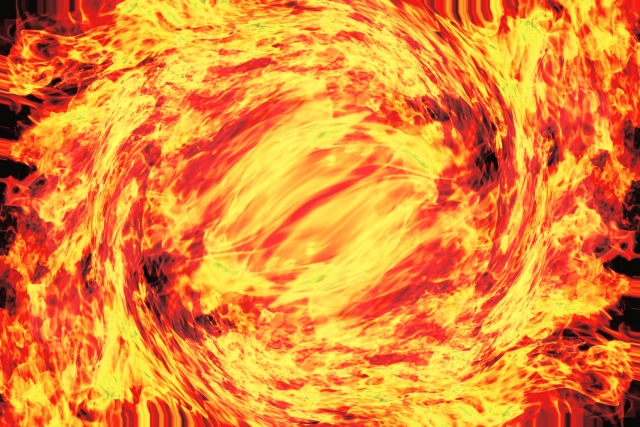
これは私が上京して初めて働いた職場での一コマである。
社員A:「そういえば、早川君って東京に来て体調を崩したことないよね?」
早川:「いえ、ここで働き出してから、風邪を引いたことがありますよ」
社員A:「え!? 本当!? でも君がマスクをつけているところは見たことないよ」
早川:「はい。マスクをつけていたら風邪を引いていることがバレて帰されると思ったから、風邪を引いていることを隠すために、マスクをつけていませんでした。それに『風邪を引いても頑張って出社してます』アピールする人ってカッコ悪いじゃないですか?」
社員A:「ちょっと!! そんなことをしたら他の人に風邪が移るかもしれないでしょ!! そんなことをされる方が、一日や二日休むよりも遥かに迷惑なんだけど!!」
早川:「悪いけど、こっちも生活がかかっているんで、そこまで気を配る余裕はありません。もし、風邪で休んでも給料が出るのなら、喜んで休ませてもらいます」
社員A:「早川君って利己的なのか、健気なのか分からないね」
早川:「ハハハ」
という話をしていると同僚の社員Bが話に加わってきた。
社員Aは私が風邪を隠して出勤していた時のことを話しているのだと伝えた。
すると社員Bは実にうれしそうな顔で食いついてきた。
「え!? そんなこと普通だよね??」
「俺だって風邪で休んだことなんて一日もないんだよ??」
「インフルエンザにかかった時だって2日で復帰したよ??」
それを聞いた私は
わー!! 出た!!
奴隷の鎖自慢!!
…と言いたかったが、社員Aがいる手前、その言葉を発するのには自重した。
中学生の時以来だから十数年振りだろうか、脊髄反射的に「キモい」という言葉が頭に浮かんだ。
いや、私は「風邪を引いていることを隠して出勤している」のであって、あなたみたいに「風邪でも休まない自分はカッコいい」アピール全開の人と全然違うんですけど。
あなたなんかと一緒にしないで欲しい。
あなたみたいな人は尊敬するどころか、心の底から軽蔑しています。
つーか、見事なまでの「飛んで火に入る夏の虫」状態なんですけど…
・不幸自慢と弱い者いじめ

先のBほどバカではないにせよ、このような「奴隷の鎖自慢」、あるいは「社畜の不幸自慢」と呼ばれる
・残業自慢
・数週間休んでいない自慢
・病欠しない自慢
をしてしまう人を見かけるのは珍しくない。
だが、他人の不幸自慢を聞いて、「あの人は自分よりも頑張っているんだなあ」、「彼に比べたら自分なんてまだまだ甘い」と感心する人などいないと思う。
自分の不幸自慢をやめられない人でも、それは同じではないだろうか?
これは「いじめ」と同じで、「頭では悪いと分かっているのだけど、やめられない」状態であり、ハッキリ言って、心の病気ではないかと思う。
この手の話題となると、先ほどのBのように喜び勇んで話に飛び込んでくる人が多い。
私はこれらの不幸自慢の裏には「自分はこんなに頑張っている」という自己顕示欲だけでなく、「自分はこんなに苦労しているのに、そんなことで文句を言うことが許せない!!」というような憎しみに満ちた権利意識を感じてしまう。
さて、この病理を解明してくれる本がこちら。
内藤朝雄(著) 柏書房
この本では
・そもそも、「いじめ」とは何なのか?
・加害者の目的は何なのか?
・なぜ、当事者たちは「いじめられる方にも原因はある」と思ってしまうのか?
・一人でいる時は「いじめは悪い!!」と分かっていても、なぜ集団になると「いじめが楽しい」と思ってしまうのか?
・なぜ(被害者ではなく)加害者の方が被害者意識を持っているのか?
・どうすれば、いじめの蔓延を防ぐことができるのか?
ということを学術的に説明している。
いじめについて知りたい方はぜひともこの本を読んでほしい。(このブログでも稚拙ながら解説記事を書いている)
ここでは今日のテーマである「奴隷の鎖自慢」を解明してくれそうな「過去の自分を癒すためのいじめ」のメカニズムを見ていこうと思う。
・被害者が加害者へと変わる時

この本でたびたび現れる重要なワードとして「全能感」というものがある。
これは「何でもできそうな無限の力に満ちてたような感覚」だと考えてもらいたい。
人が逃げることができない環境で圧倒的な力を持った強者に痛めつけられている時は、「痛めつけられていること」自体を「戦っていること」のように思い込むことで、「今の自分は戦っているのであって、いじめられているのではない」と自分に言い聞かせて自尊心を守ろうとすることがある。
この時は「相手は自分をいじめていて、自分はいじめられている」という実像は見て見ぬフリ、知っているけど知らないというような形で凍結して「耐えることで戦っているので、自分はいじめられているのではなく、相手も自分をいじめているのではない」と思い込んでいる。
このように「耐えることで戦っている」という「タフの全能感」を持つことで現実のみじめさを否認する。
苦境が過ぎ去ると「自分は耐えることで強くなった」というようにタフになることの美学に浸る。
フィクションでは大体このあたりで完結して「あ~、よかったね。めでたし、めでたし」となるのだろうが、現実には続きがある。
このような体験加工を行い、耐え抜いたことを誇りに思うだけなら結構なのだが、頭の中には凍結していたはずの「自分をいじめる強者ーいじめられる弱者としての自分」という実像はうっすらと残っている。
だから、かつての自分と同じ立場の人が、自分と同じように苦しまないと、「自分は耐えることで戦った」という権利意識から手痛い攻撃を加えずにはいられなくなる。
そして、自分の方がいかにひどい目に遭ったのかを必死に語り、自分が攻撃しているにもかかわらず、散々偉ぶって弱者の心のありかたを説教して、かつての自分と同じように耐えて戦うことを強制しようとする。
何でこんなことをする必要があるのか?
それは、以前の自分と同じ立場の人が同じように苦しんでもらわないと「弱者でありながら耐えることで戦った」とか「耐えることで強くなれた」というような図式と自意識が崩壊してしまい、「かつての自分は戦っていたわけではなく、単にいじめられていただけ」だということがバレるからである。
だから、明らかに加害者に非があるケースでもそれを認めることができず、自分と同じように耐えることができない被害者を非難し続ければならない。
たとえば、ブラック企業問題が議論になると必ず言われることが、
「たとえ法律違反でも、それくらいのことは当たり前だ!!」
「自分はもっと酷い目にあった!!」
「そんなことで文句を言う労働者は甘えている!!」
「最近の若いやつは甘えてるいから、自衛隊に入れて鍛え直せ!!」
と自分の方が酷い目に遭ったことを必死に訴えて、経営側の人間でもないにもかかわらず、犯罪企業を擁護して、虐げられている労働者を非難することがある。
これも同じような理由で行っているものと思われる。
彼らのように「耐えて強くなった」と自負している人間は、たとえ、企業が法律違反を犯していると分かっていても、「不正を行う強者の存在」は見て見ぬフリして、被害者に(かつての自分と同じように)耐えることを強制しないといけないのである。
ちなみに、自分が強者になると、自分がかつてされたことと全く同じことをしてしまうのは、弱者にかつての自分を投影するだけでなく、(自分を痛めつけていた)加害者に自分を投影して、自分が受けたいじめを散々行って「自分はいじめる強者の側だから、いじめられている側ではない」と確認して安心する、過去の体験を癒す営みでもある。
彼らがいじめに向かう唯一の動機は「弱い自分を認めたくない」ということだけである。
これが、かつていじめを受けた人物が、「自分がいかに辛い目に遭ったのか」を必死になって語り、自分と同じように苦しまない人を見ると手痛い攻撃を加えずにはいられない理由である。
・はき違えた強さなど断じて認めてはいけない

奴隷の鎖自慢はこのように「耐えることで戦って強くなった」ことを誇る「タフの美学」と権利意識から来ているものと思われる。
だから、自分が耐えることで強くなったことを誇る奴隷の鎖自慢が進化(人間としては退化)して、他人にもかつての自分と同じように耐えることを強制しようとする人間に対しては、負の連鎖を断ち切るためにハッキリと言ってやろう。
「お前は戦ってなどいないし、強くなってなどいない!!」
「弱い者いじめしかできず自分が加害者であることを誇るゲス野郎のド変態が!!」
(注:先ほど紹介した「いじめの社会理論」で、このようなやり方を紹介しているわけではない)
Bのような権力のない人間の場合は幸い「自慢」程度にとどまっているが、彼が改心せずに社内での高い地位を獲得したら(もっとも彼の能力では不可能だろうが)、今後は弱い者いじめに手を出す危険性が高い。
「苦しいことに耐えて強くなった」と自負するのは結構だが、その後の立ち居振る舞いでこそ本当の強さが分かる。
・今日の推薦本①
学術書である「いじめの社会理論」を一般向けの言葉で説明してくれる新書。
正直に告白すると、私も最初はいじめの社会理論を理解できなかったため、こちらの本を読んでから改めて読み直した。
・今日の推薦本②
上で紹介した「いじめの構造」をさらに優しい言葉で説明する本。
著者のいじめ研究の原点とも言える体験談も多く収録されているので、「いじめ理論」については簡単なものしか紹介されていないが、中学生くらいの年齢の人にもおすすめできる本である。