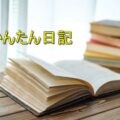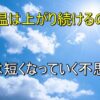先日の日曜日は東京都議会議員選挙の投票日だった。
投票日の1週間ほど前から、最寄り駅では朝の通勤時間帯も、夕方の帰宅ラッシュも、毎日のように候補者や支援者が街頭演説を行っていた。
その中には、耳を疑うような差別的な発言を繰り返し、大衆の不満や怒りを煽るだけの大バカ者もいた。
一方で、誠実に、地道に、自分の考えを言葉にしながら、聴衆に語りかける候補者もいたことは否定しない。
地域の課題や政策の方向性について必死に説明する姿は、まさに「政治家」であると感じられた。
そうした演説を耳にすると、「ぜひこの人に投票したい」と思うこともあった。
しかし、誠に残念だが、私はそんな彼らに投票することはなかった。
なぜなら…
私の居住地は最寄り駅とは別の選挙区だから…
その候補者がどれほど素晴らしい政策を訴え、私がどんなに彼らに共感できたとしても、残念ながら、私は彼らに一票を投じることができないのだ。
これは、意外と多くの人が経験している「もどかしさ」ではないだろうか。
自分が住んでいる行政区の外で、理想的な政治家に出会っても、選挙権は市区町村単位で区切られているため、応援はできても投票はできない。
北海道や九州のような(都内在住の私から見れば)遠隔地が選挙区である候補者ならまだしも、毎日のように見かけ、手を伸ばせば届きそうな所にいる人たちですら、この壁に阻まれているのは非常に歯がゆい気持ちになる。
もちろんこのような仕組みは、合理的な理由があって存在しているのだろう。
選挙は、地域の代表を選ぶ行為である以上、その地域に住んでいる住民こそが意思を示すべきという考え方は一理ある。
だが、現代の都市生活では、最寄り駅や生活圏が必ずしも住民票のある場所と一致するわけではない。
むしろ、職場や日常生活の多くを過ごすエリアと、自分の選挙区が異なるというケースは少なくない。
例えば、職場がある区で日々の暮らしをしている人にとっては、その地域の政治や政策は、自分自身の生活に直結する重大な関心事となるはずである。
しかし、選挙の権利はそこにはない。
これでは、政治に関心を持っても、それを行動に移す手段が与えられていないようにすら思える。
そう考えると、街頭演説そのものの「効果」についても、疑問が湧く。
今回のように、通勤の途中で耳にした演説に心を動かされても、選挙区が違えば意味をなさない。
もし演説をしていた候補者自身も、それを理解したうえで訴えていたとしたら、その行為は一体誰に向けられたものなのだろうか。
選挙区内に住んでいる有権者も一定数その駅を利用しているのだろうが、演説の多くが「届かない人々」にも向けられている気がしてならない。
もちろん、街頭演説には全く意味がないとは思わない。
しかし、その有効性や影響力が、選挙制度の制約によって限定されてしまっている現実も、もっと議論されてよいのではないかと思う。
特定の区だけでなく、例えば「生活圏」という新たな区割りの考え方や、応援したい候補者に意思を示すための「推薦投票」といった制度があってもいいのかもしれない。
「この人に託したい」と思う心と、それを行動に移せない制度のはざまで、私たちはどれだけの政治的可能性を失っているのだろうか。
今回の選挙では、そんな問いが頭をよぎった。