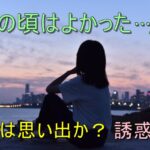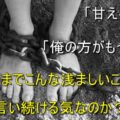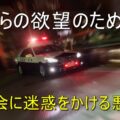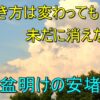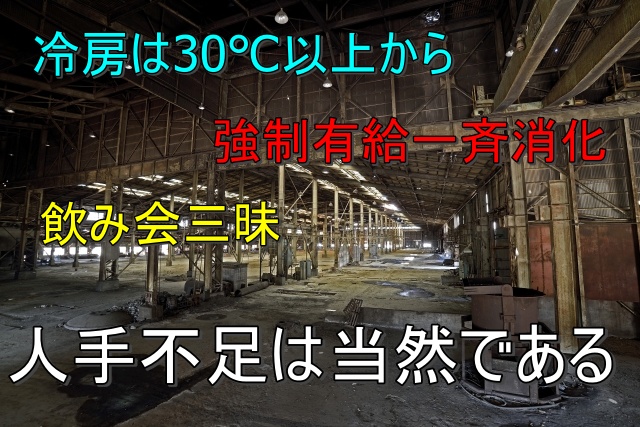
前回の記事で、2年前に勤めていた会社でお盆期間中に有給休暇を強制的に一斉使用させられた話をした。
この会社では他にも労働条件や職場環境に不満があり半年で退職することになった。
だが、お盆休みの有給消化以外の不満については、10年ほど前に働いていた職場でもかなり似たような経験があった。
・事務でも製造現場でも同じこと

その会社とは、過去に何度か取り上げたことがある地元の工場である。
この時は製造現場、2年前は事務職という違いこそあるものの、どちらも製造業という点においては共通している。
10年前に製造現場で働いていた時は単に「嫌な会社に入ってしまったな…」くらいにしか思っていなかったが、2年前に働いた職場で同様の出来事を体験したことで、「これはたまたまあの会社が酷い環境だったわけではなく、製造業全般に共通しているのではないか?」と感じるようになった。
ここで両社に共通していたことをいくつか取り上げたい。
①:徹底したコストカット
2年前に働いていた会社では冷房は室温が30℃を超えないと付けてはいけないという規則があった。
冷房の温度も28℃までしか下げさせない。
というわけで、真夏でも扇風機が頼りだった。
しかも、自腹で購入した物を各々の机に取り付けなければならないというケチっぷり。
10年前の会社は冬に働いていたこともあり、冷房については直接的な被害を受けたわけではないが、「冷房の設定は28℃まで」という注意書きがあったので、おそらく夏場は同様に使用制限がかけられているのだろう。
設定温度が28℃と共通しているのは偶然なのだろうか?
ちなみに、2年前の職場に至っては、休憩時間は作業部屋の電気が消され、自席で過ごす場合は灯かりなしで過ごさなければならないという掛け値なしの守銭奴ぶりだった。
また、掃除は外注ではなく社員自身が行い、ゴミ袋の空き容量に余裕がある常態で捨てると鬼の首でも取ったかのように「コスト!! コスト!! もったいない!!」と大騒ぎ。
製造業といえば、低価格で高品質な製品を開発・販売するために、コストを極限まで削減しているというイメージがあるが、そのしわ寄せが来ているのだろうか?
経費削減がここまでくると、とてもではないが労働に適した環境とはいえない。
②:毎朝のラジオ体操と長ったらしい朝礼
小学生の時は夏休みや運動会の練習でよくラジオ体操をさせられたが、この歳になってまで同様のことをさせられるのは恥ずかしいし嫌でしょうがない。
しかも、その後は形式的な挨拶や前日の出来事報告、どうでもいい雑談のような安全唱和で時間が浪費される。
毎朝仕事前にそんなことをさせられたらやる気がなくなる。
生産効率を重んじるはずの業界が、なぜ朝から非効率な儀式に時間を割くのか理解に苦しんだ。
直接働いた経験はなくても、求人内容を見たり、面接で話を聞いたところ、毎朝ラジオ体操と10分近い朝礼が行われる企業の多くは製造業(または建設)だったことから、これは業界全体の悪しき習慣なのかもしれない。
③:飲み会や社内イベントが盛りだくさん
業務時間外の懇親会を「仕事の一部」とする価値観が残っており、参加しないと冷ややかな目で見られる会社は少なくない。
製造業は特にその傾向が強い気がする。
しかも、年一回の新年会や忘年会だけならまだしも、2年前の職場は毎月末に当月の反省会と翌月の目標を出し合う決起集会と称した飲み会が、10年前の職場では当月生まれの人の誕生会など、毎月何かと理由を付けてイベントが行われていた。
属性に基づく発言はよろしくないが、中高年男性が多い職場ほどこの傾向は強く、プライベートの自由は軽んじられるのだろう。
ただ、どちらの会社も参加費の自己負担を求めることなく、すべて会社費用で行われたことから、最低限の良心は残っていた。
驚くべきことに、この社会には参加を強要しながら、当然のように自己負担とする会社も存在するのだ。
④:邪魔でしかない小休憩
両社ともに午前と午後に10分間の一斉休憩が設けられていたが、それがあるせいか、それ以外の時間は席を外しづらい。
当然ながら、休憩時間の給与は控除される。
さらに全員が同時に休憩するため、トイレは常に混雑する。
ちなみに、2年前に働いていた会社は事務職だったため私は無縁でいられたのだが、その会社の製造現場では、休憩時間だというのに喫煙や水分補給にも制限が設けられていたとのこと。
給料は控除されているのに、それは「休憩」とは言わないだろう!?
この件についてはこちらの記事にも詳しく書いてある。
⑤:創業者を神様のように崇拝させられる
②と重複する部分もあるが、10年前に働いていた会社では、毎朝ラジオ体操と職場での全体朝礼が行われていた。
その間に別の場所にいる創業者とテレビ電話で繋がり、彼の思い付きや時司ニュースの感想などのどうでもいい話を長々と聞かされた。
多くの人が職務として自分の指示に従うことを「自分が人間として優れているから、その教えを乞うている」とでも勘違いしているのだろうか?
ただ、後に「これはボケ老人の戯言に付き合っているだけ」に過ぎないのだと実感した。
2年前の職場はもっと酷く、勤務初日に創業者の理念や企業として、社員として目指す姿が書かれた本(結構分厚い)を渡されて、朝礼でその本の一節を読み合わせさせられた。
その他にも、社内のいたる所に「○○(創業者の名前)イズム」と称した彼の理念と、それに少しでも近づくための心構え、「急ごう、さもないと会社も地球も滅びてしまう」というどこぞの工場の通路に書かれていたフレーズのように、従業員をハードワークを課す標語が書かれたポスターが貼られ、それについて来られない人物は社内に不要と断言していた。
このような個人崇拝ははっきり言って、
キモすぎる。
ここは北朝鮮か、それともロシアか?
この創業者だが、社内では「レーニン・○○」とあだ名を付けられていた。
ソ連国歌の歌詞に「偉大なレーニンは我々に進路を照らし」という個人崇拝が含まれ、反対する者を粛清するという政治手法が似ていることが由来らしい。
・「製造業は日本の主産業だ!」と言うのなら

このように、現場作業と事務職の両方を経験したが、共通していることはかなり多く、私は製造業には二度と戻らないと決め、知人から「製造業で働こうと思う」と言われれば全力で止める。
現在、日本の製造業は慢性的な人手不足に陥っている。
経済産業省の統計によれば、2002年には384万人いた34歳以下の製造業就業者が、2023年には259万人まで減少した。
割合にして31.4%から24.5%への低下である。
20年余りで若年層が121万人も減った計算だ。
有効求人倍率を見ても、製造業の生産工程従事者は1.67倍と全体の1.25倍を大きく上回っており、求人を出しても人が集まらない現実が浮き彫りになっている。
中小企業庁の調査では、中小製造業の59.4%が「人手不足を深刻」と回答している。
理由は明白で、多くの労働者が製造業を敬遠しているからである。
そして、彼らの判断は間違いなく正しい。
製造業を日本の根幹のように捉え、昨今の人手不足を「若者の怠け癖」や「仕事の厳しさへの甘え」とする声もある。
しかし、実際は業界側が人を遠ざける環境を作ってきただけだ。
快適さや働きやすさを犠牲にしてまでコストカットを続け、旧態依然の上下関係や集団行動を押し付け、自由な時間や有給取得の権利を削ってきた。
これで「若者が来ない」「人手不足だ」と嘆くのは、責任転嫁に他ならない。
現場の生産性を高めたいなら、本来は社員の体調管理や作業環境の改善に尽力しなければならい。
暑さや寒さのストレスを減らし、柔軟な休憩やシフト制度を導入するほうが、長期的には離職率を下げるとか。
だが、短期的なコスト削減に囚われ、従業員には「カイゼン」を要求する一方で、自身の反省や改善を怠った結果、今の人材危機を招いている。
何とも滑稽である。
製造業を守りたいのなら、彼ら自身が変えなければならない。
不要な朝礼や飲み会は廃止し、空調や休憩制度を改善する。
有給を自由に使えるようにし、勤務形態を柔軟にする。
「これが製造業の伝統だ」と言って変化を拒む限り、若者離れは止まらないし、彼らの宿願である「物づくり大国ニッポンの復活!!」など絵に描いた餅に終わる。
彼ら自身が「自分たちが変わらなければ」と自覚しなければ、この人手不足は解消するどころか、より深刻化していくことだろう。