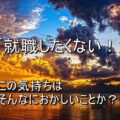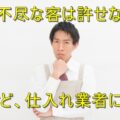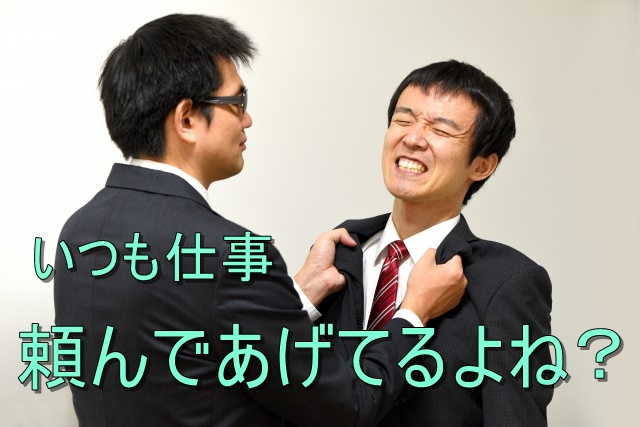
働いている人であれば、職場でこんな言葉を耳にしたことがある人は少なくないだろう。
「持ちつ持たれつ」
ビジネスの場においては、長い期間かけて構築する信頼関係があり、場合によって、それはお金や契約といった市場の原理よりも優先される。
たとえば、
-
従業員は労働基準法違反の命令を受け入れる代わりに、どんなに仕事ができなくても、経営者は絶対に解雇しない。
-
納品先はかなり無茶な要求を押し付けてくるが、他社がどんなに安い製品を販売しても、絶対に目移りしない。
というように。
そして、そのような契約外の要求が通ることは「融通が効く」と呼ばれている。
このような「契約」よりも「情」を重視する取引が「日本の良さ」のように語られることが多々あるが、私は「持ちつ持たれつ」や「融通」といった言葉が好きではない(というよりも「嫌い」だ)し、無条件に称賛することは危険だと思っている。
今日はその話をしたい。
・都合がいい時だけ「お店の一員」

私が職場で「持ちつ持たれつ」という言葉を初めて耳にしたのは24歳の頃だった。
この記事で紹介した職場で働いていた時である。
その職場はディスカウントストアにテナントを出店する小売店で、表向きの営業形態は「ディスカウントストアの一部門」という顔をしていたが、経営は完全に分離していた。
もちろん、私たちテナントの人間はディスカウントストアから用具の支給もなければ、仕事を手伝ってもらうこともない。
だが、店長であるカワグチ(仮名)は、私にディスカウントストアや他のテナントとの協調を訴えた。
たとえば、客から商品のことを聞かれたら、自分の部門でなくとも案内するとか。
一人で働いている時でも、すぐに呼び出しに対応できるように、昼食は外ではなく、作業場で取るとか。
その時、彼は私たちとテナントの関係を「持ちつ持たれつ」という言葉で表現していた。
実際に私たちは従業員2人で細々と切り盛りをしていたため、彼らのサポートは必要不可欠である。
それを考えると、それくらいの要求を受け入れることは仕方ない。
しかし、蓋を開けてみたら、それは「持ちつ持たれつ」というような対等な関係ではなかった。
彼らは、私たちにディスカウントストアの従業員として客に接することを求める一方で何をしてくれたというのだろうか?
クレームの対応をしてくれたり、人手不足で店が回らない時に手伝ったり、営業休止を認めるわけでもなく、終始、「ウチとは別会社なんだから、自分たちだけで責任を持って対応してください」という冷たい態度だった。
これでは、「持ちつ持たれつ」ではなく、一方的に「もたれ掛かられる」だけであり、もっと言えば、「植民地支配」ではないのか?
私はこの時、初めて「搾取」という言葉の意味を知った。
ちなみに、ディスカウントストアとの関係は完全に支配と服従だったものの、他のテナントとは鍵の貸し借りや、互いに売れ残った商品のおすそ分けをしたりと良好な関係だった。
皮肉なことだが、店長が言っていた「持ちつ持たれつ」は、ディスカウントストアではなく、他のテナントとの間で実感できたのである。
・あんたがそれを言うか!?

今度は工場で働いていた時の話。
その時の納品先は5社ほどあったが、その中の1社だけが、「仕事を頼んでやっている」というような恩着せがましい態度で、ズケズケと細かい(そして、しつこい)クレームを付けていた。
私が同席したわけではないが、工場で連中も同席する会議が行われた時に、言いたい放題言われた工場長が涙目で「あそこの店長、マジで態度悪い…」と愚痴っていたことがあった。
そんなわがままな人たちでも、「いつも注文してくれているから…」という理由で私たちは要求に応じていた。
ある日、大雪が降って、工場が丸1日稼働できないことがあった。
翌日には営業再開できたが、どうしても仕事が追い付かないことが見込まれ、工場長が取引先に電話をかけて、納品日の延期や納品量の調整を交渉した。
常識的に考えれば、「こんな時、真っ先に要求を受け入れてくれるのは誰か?」というのは一目瞭然である。
それは、普段はわがままを言っている人たちである。
いつも、融通を利かせているのだから、これくらい受け入れてくれるに違いない。
だが、実際は全くの逆だった。
彼らは工場長の必死のお願いに対して、
「そんな事情、ウチには関係ない!!」
「ウチの売り上げが下がったらどう責任を取るんですか!?」
と言って、一歩も引かず、私たちは長時間の残業を余儀なくされた。
普段は契約外のことも、あれこれと要求してくるにもかかわらず、こういう時は契約内容の厳守を要求するとは何というずうずうしさだろうか?
実に破廉恥で自己中心的なモンスター企業である。
昔、ある地域の人たちのことを「ゆすり・たかりの名人」と誹謗した人がいたが、その言葉はこのような人間に向けるべきであろう。
彼らは「顧客」ではなく「乞客」であり、私たちのことを完全にナメ切っていたのである。
ちなみに、他の4社は全員が、私たちの事情を理解してくれて、「自然災害なので、仕方ないですね」と言ってくれた。
これこそ、真の意味で「融通を利かせてくれる」ではないのか?
普段は契約外のことを口出ししない彼らがそれをやってくれることは、嬉しいことだが「正直者がバカを見る」の典型のようで複雑な気持ちだった。
ちなみに、その内の1社は意外にも前段で紹介したディスカウントストアだった。
テナントには厳しいけど、取引先には優しいという意外な一面が垣間見えた。
もっとも、取引していたのは別の店舗だったが…
・本当の「持ちつ持たれつ」とは

ここまで、「持ちつ持たれつ」や「融通」という言葉を否定的に見てきたが、もちろん、そうではない場合もある。
これはあくまでも噂であることを断っておくが、地元に住んでいた時に聞いた話である。
地元で有名な大手バス会社は路線バス、高速バスに加え、観光バス事業も展開していた。
だが、その会社で観光バスを貸切るには、ローカルの会社に比べて2倍ほどの費用が掛かり、多くの会社や団体は見積もりを見ただけで、ドン引きするレベルらしい。
そんな中でも、バスを貸切る時は決まってその会社を利用する団体があった。
それは私が通っていた小学校である。
私が通っていたのは公立の小学校だが、自宅から学校までの距離が2km以上の児童はバスで通学していた。
彼らが通学する時間帯はバス会社も採算性を度外視して、多めにバスを走らせてくれていた。
その見返りとして、小学校がバスを貸切る時は、毎回その会社に依頼することになっていたのだ。
思い返すと、私も小学生の時は、その会社の観光バスに何度も乗車したが、小学校を卒業すると全く利用しなくなった。
このような形の「持ちつ持たれつ」であれば、私も全然文句は言わない。
しかし、前段2つで取り上げたように、この世の中では、ゆすり、たかり、弱い者いじめの常習犯が好んで使うケースが圧倒的に多い気がする。
最近は多くの品物の値上げが起きている。
普段は散々、下請けや取引先に無茶を言っている人たちは、営業担当者から値上げを要求された時に、「まあ、いつもはこっちが無理を言っているから」と笑顔で値上げを受け入れることができるだろうか?
「その価格だったら、もう取引はしません!!」
「他社の見積もりではこの値段ですよ!!」
自分たちはわがままを言っておきながら、こんな金のことしか考えない浅ましい言葉が出てくるのであれば、普段の言動は「持ちつ持たれつ」ではなく、ゆすり、たかり、弱い者いじめです。