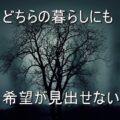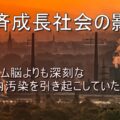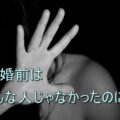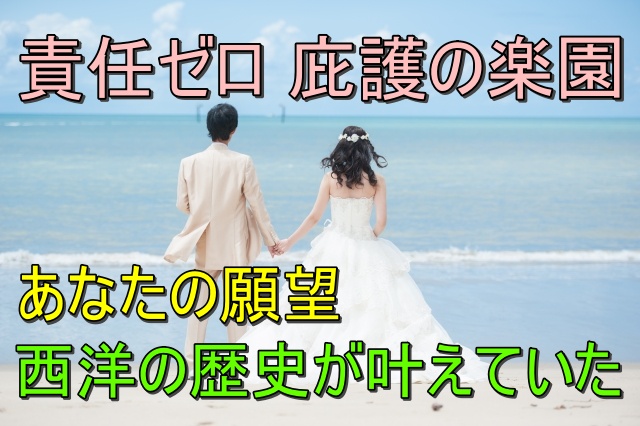
2025年10月、高市早苗氏が第104代内閣総理大臣に就任した。
決断と前進の高市内閣が発足 | お知らせ | ニュース | 自由民主党
日本の総理大臣に女性が就任することは初めてである。
ちなみに、政治とは全く関係がない話題がテーマだったが、「高市氏が総理就任となるか?」については4年前にこの記事で一度触れたこともあった。
「男女平等」や「女性の社会進出」という言葉が日本社会に出て、もう40年以上くらい経過しているが、それでも長らく女性の首相は現れなかった。
彼女はそんな中で、キャリアを積み重ねて「ガラスの天井」を打ち破り、国のトップに上り詰めた。
・バリバリ働くキャリアウーマンよりもお姫様になりたい

高市氏の首相就任は、同じように男社会で苦しみながらも、必死に努力している女性にとっては、大きな励ましとなったことだろう。
しかし、「彼女のように、並の男以上にバリバリ働いて、出世することを望む女性が大半なのか?」と言われたら、そうでもない気がする。
むしろ、そうした動きに逆行するように、責任ある地位で働くことを拒否して、「結婚して専業主婦になりたい」と願う声が日に日に大きくなっている。
もちろん、人生の価値観は人それぞれであり、誰もがキャリア志向である必要はないし、「仕事よりも家庭を優先したいから主婦になりたい」という選択も尊重されるべきだ。
だが、彼女たちの中には「働きたくないから、自分を養ってくれる男と結婚して、夫が稼いだお金を自分のものとして自由に使いたい」と言っているようにしか聞こえない者もいる。
彼女たちは無邪気に「自分を溺愛してくれて、仕事をさせず、お姫様扱いしてほしい」と言っているのかもしれないが、そのような主張こそ、最も専業主婦を愚弄していると言える。
ちなみに、このようなメンタリティの人たちは、男性へ期待値が異常なほど高く、相手と対等な関係で言葉を交わすことを拒否して、「自分は男性の庇護下に居るのだから、これくらい分かってよ…」と言葉を持たない子どもや、感情の機微で相手との関係を調整する動物のように、態度で察してもらうことを好む傾向があるように思える。
しかも、恋愛映画やマンガの影響か、「海外、特に西洋の男性はそれが出来て当たり前」と根拠に乏しい迷信を唱えて、そうしてくれない周囲の男性に不満を持つ。
そして、自分のことを分かってもらえない場合は、相手への一方的な憎悪を募らせて、解決するよりも、逃げ出すことを選び、相手が心配して探そうものならストーカー扱いして、「本当はずっと我慢していたんだ!!」とどこまでも被害者ヅラ。
彼女たちは結婚を望むが、こんなわがままで依存心の塊で、都合が悪くなったら、逃げ回って誰かに守られることしか考えていない女と付き合うことは大変であり、そんな女と結婚することを願う酔狂な者など何所にいると言うのだ。
誠に嘆かわしい。
とはいえ、そんな彼女たちに朗報がある。
実は、彼女たちの望む生き方に非常に近く、ぜひともおすすめしたい制度がかつて西洋に存在していた。
・支配ではなく、保護と二体一身が目的

以前、この記事で登場したこともあるが、中世から20世紀にかけてヨーロッパには「カヴァチャー(coverture)」と呼ばれる制度があった。
これは、英米法(コモンロー)における伝統的な婚姻法理で、妻が夫の「庇護(cover)」の下に入り、法的に一体となるという考え方である。
名前の通り、「cover(覆う)」という語源を持ち、「妻は夫によって覆われた存在」とみなされる。
この法理の本質は、現代の婚姻制度のように「夫婦それぞれが独立した個人である」という前提とはまったく異なり、結婚した瞬間、妻は独立した存在ではなくなる。
カヴァチャーの下では、妻は単独で財産を所有することも、契約を結ぶことも、裁判の当事者になることもできない。
すべての法的行為は夫を通して行われる。
つまり制度上、妻は夫の「影」であり、ひとりの大人の人間としては扱われない。
もし妻が誰かに損害を与えたとしても、それは妻の責任ではなく夫の責任になる。
逆に妻が被害を受けても、訴えるのは妻ではなく夫である。
妻本人は、法律上「訴える」という行為も「訴えられる」という行為もできないからだ。
カヴァチャーは、中世・近世の社会においては「妻を外の危険から守るため」と説明されてきた。
妻が外界で何かを決めたり行動したりする権利を奪うことで、同時に責任や義務もすべて夫が負う形にしていた。
「権利がない代わりに責任もない」という極めて徹底した庇護の構図が浮かび上がる。
カヴァチャーの目的は支配ではなく、あくまでも結婚や家族を通じた女性の保護と「夫婦は二体一身」という価値観によるものである。
カヴァチャーの象徴的な言葉として、「夫婦は法的に一人の人間であり、その一人とは夫のことである」という表現がある。
妻には個別の意思決定権はなく、人格の主体は夫が代表する。
妻がどのような価値観や考えを持っていても、法的には反映されない。
つまり「夫と対等に話し合う」という前提すら存在しなかった。
ただし、重要なのは「これはあくまでも既婚女性のみが対象だった」という点である。
「女は男よりも、バカで劣った存在であり、男と同等の権利なんて認めたら、とんでもないことになる!!」という女性差別に基づく考えから生まれたのであれば、女性全員を対象にすることが自然だが、未婚女性は法的に独立した人格を認められていた。
現実には経済的・社会的制約で難しかったが、少なくと建前としては「結婚しなければ、女性は普通に自立した個人として生きられる」という選択肢も成立していたのである。
・男に依存する道を望むのなら、どうぞその道を突き進んでください

現代の人権意識から見ると、「女性が結婚したら、すべての権利を失い、夫に従属しないと生きられない」というカヴァチャー制度はとんでもないように思える。
だが、この制度を依存志向の女性の願望に照らしてみると、その願望を驚くほど忠実に叶えてくれるものではないだろうか。
まず、カヴァチャー下の妻には権利がない。
これは一見、搾取されているように思えるが、裏返せば「社会的な責任を一切負わないで済む」ということでもある。
自分名義の財産も契約もなく、何かトラブルが起きても法的には夫が責任を負う。
まさに「守られていたい」、「責任を負いたくない」という願いにぴったりではないか。
次に、夫と一体の存在という点。
妻は夫の法的影であり、個別の意見や意思決定を必要としない。
つまり、対等な主体としてコミュニケーションを取る必要がないのだ。
子どもや動物のように態度で察してもらって、不満があっても口を開かずに、ずっとブスっとした表情で拗ねてさえいればいい。
その上、この制度はれっきとした西洋発祥だ。
西洋文化に強い憧れを抱き、「海外の男性は女性に優しい」と信じて疑わない彼女たちにとっては、まさにそんな西洋社会で長く用いられていた婚姻制度なのだから、「望む理想の形」として相性抜群である。
そして何より重要な点は「カヴァチャーは女性自身が選ぶかどうかの選択権があった」ということ。
自立を拒否して、男の庇護下に入る生き方を望むなら、自ら進んでそうした身分になることが出来た。
依存型の恋愛観や「男に守ってほしい」、「難しいことは考えたくない・責任取りたくない」という願望を、歴史上もっとも徹底した形で制度化したものが、このカヴァチャーと言えるのだ。
もちろん、現代日本の結婚制度に満足している人もいるから、結婚制度をカヴァチャー制に変更することは不可能である。
しかし、従来の結婚制度とは、義務も権利も異なる「カヴァチャー婚」を新設することは可能ではないだろうか。
カヴァチャー婚を選択すると、女性は男性の庇護下に入り、すべての権利を失うが、同時に社会的な責任を負う必要も一切ない。
当然、労働は不要、難しいことも何も考えなくて良いし、話し合う必要もない。
すべては夫任せで、自分は夫についていくだけ。
もちろん、家長である夫は妻の躾けを好き放題できることが出来て、妻はそのことに異議申し立ては出来ない。
社会からは隔絶されるが「権利なんて要らない」、「責任を負いたくない」、「難しいことは何も分からなくていい」、「男に守られたい」、「何も言わず察してほしい」という価値観がある人にはピッタリである。
自立を拒む察して系女子の皆様!
「男女の関係は対等」なんてクソ甘ったれたことを言っている現代の軟弱な日本男子など見切りをつけて、逞しい男に徹底的に守ってもらえるカヴァチャーの世界で幸せを掴もうではありませんか!!
え?
「奴隷みたいで息苦しい」、「あまりにも惨め」ですって?
良いじゃないですか、そんな些末なこと。
だって、あなたが望んだ道なんでしょう?
それが嫌なら、甘ったれたこと言わないで、一人前の大人になってください。
なにも「高市総理のように国のトップに立て!!」と言っているわけではない。
依存を望むのであれば、対等な扱いを求めたり、社会の便宜だけ享受する「美味しい所取り」は出来ないという当たり前の話をしているのである。
どの時代であれ、どの社会であれ、自分で選んだ生き方には必ず相応の条件と代償がついてくるのだから。
腹の底まで腐りきった甘ったれには、そんな当たり前のことすら分からないのかもしれないが。
次回の記事も同じように「愛されたい!!」と願う人がテーマとなる。