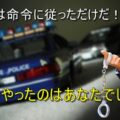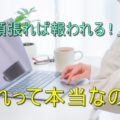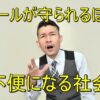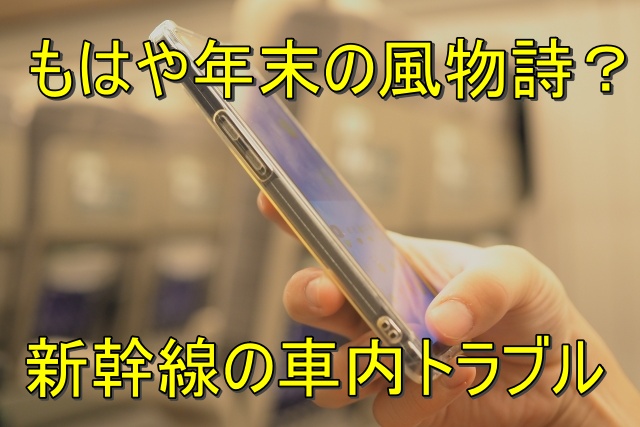
2025年も残り2ヶ月になり、段々と年末年始が近づいている。
この時期に考えなければならないことは、年末年始の帰省の準備である。
・利用される交通機関は他にもあるはずだが…

ニュースやSNSで「帰省ラッシュ」、「乗客トラブル」といった話題を目にする。
年明けを地元の家族と共に過ごす時間は何事にも代えがたい幸福であるが、そこへ至る、またはそれを終えた後の移動についてはいろいろと気が重い出来事も起きる。
混雑や遅延だけならまだしも、「マナーを守らない乗客と遭遇してストレスを感じた!!」たというエピソードも少なくない。
-
自分が予約したはずの席に違う人物が座っており、注意したら逆ギレされた。
-
子ども「窓際の席の方が良いと言っているから」と、変わって欲しいと言われた。
-
前の席の客がいきなりリクライニングを倒して、危険な思いをした。
-
席は空いているのに、その前に大型の荷物やベビーカーが置いてあるから座れない。
その他にもまだまだ沢山の体験談を耳にする。
自分の体験でなくても、そんな話を聞く度に気が重くなってくる。
しかし、そうした「非常識な客と鉢合わせた」という話を見聞きしていると、どうしてもあることが気になる。
というのも、この手の話題ではほとんどのケースで、なぜか新幹線の車内が舞台になっているからである。
帰省に利用される交通機関は他にも飛行機・高速バス・在来線・自家用車と多様であるにもかかわらず、である。
きっと、新幹線は迷惑な撮り鉄だけでなく、モラルが低いモンスターも虜にして、大量に引き寄せてしまう魅力があるのだろう。
…というのは冗談だが、「なぜ新幹線だけが、迷惑行為の温床のように語られるのだろうか?」については大いに興味がある。
・ストレスやトラブルの火種になりそうなもの

まずは新幹線で迷惑行為が発生すると思われる理由をいくつか考えてみた。
・①:空間の線引きが曖昧な公共空間
新幹線の構造的な特徴として「パーソナルスペースの境界の曖昧さ」が挙げられる。
指定席があるため一見すると自分の領域が確保されているように見えるが、実際には座席のリクライニングや肘掛け、通路、荷棚といった共用部分が近接している。
つまり、「どこまでが自分の空間で、どこからが他人の空間なのか」という線引きが曖昧なのだ。
このため、リクライニングを深く倒す、通路で長時間通話する、荷物で隣席をふさぐ、といった小さな行為が他人の迷惑として目立ちやすい。
それが「車内トラブル」として認識されやすくなる。
・②:多様な乗客層がもたらす文化の衝突
新幹線の乗車券は決して安いとは言えない。
だが、バスや飛行機のように、購入時期によって変動することも少なく、一般向けの切符の発売開始も乗車日の1ヶ月前と比較的遅く、「今年は仕事の予定が読めず、1ヶ月前に帰省の予定が決まって、それから切符を買おうとしたけど、すでに売り切れていた」という可能性も低く、比較的多くの人に購入の門戸が開かれていると言える。
ということは、それだけ乗客の目的や立場がきわめて多様で、老若男女、地元民と観光客が同じ車両に同居する。
普段から新幹線に慣れている人もいれば、年に一度しか乗らない人もいる。
このように「利用頻度」や「マナー意識」に差があることで、車内での振る舞いにズレが生じやすくなる。
「リクライニングは許されるのか」、「スマホの音漏れはどこまでが許容範囲か」など、基準の違いがトラブルの火種になると思われる。
言い換えれば、新幹線は社会の縮図のような多様性を抱えた空間でもある。
・③:長時間乗車によるストレスの蓄積
新幹線は1~3時間以上の移動が一般的であり、乗客が長時間同じ空間に閉じ込められる。
「こんな車内は耐えられない!!」と思って、次の駅で降りれば、特急券の効力も失われてしまい、降りた駅から目的地まで別の列車に乗れば、新たなに特急券を購入しなければならない。
在来線の特急列車であれば、「一時降車駅から目的地までは普通列車に乗る」という逃げ道もあるが、新幹線に普通列車なく、常に特急券も必要となるため、この裏技は使えない。
逃げ場がないため、わずかな不快感が持続しやすく、結果的に印象が強く残る。
たとえ隣席の人の会話が少しうるさい程度でも、数時間続けば「非常識な乗客」として記憶に残る。
つまり、トラブルそのものよりも、「我慢を強いられる時間の長さ」が人々の怒りや不満を増幅させているのだ。
・新幹線に限った理由

ざっとこんなことが思い浮かんだ。
ただし、これらの条件は新幹線に限った話ではない。
私的と公的な空間の曖昧さ、多様な乗客層、長時間乗車によるストレスは、長距離のバスやフェリー、在来線の特急列車、飛行機など、他の交通手段にも共通する要素である。
むしろ、③の閉鎖空間で長時間過ごすという点では、夜行バスの方が新幹線よりも過酷だといえる。
それにもかかわらず、「迷惑客がいた」という話は新幹線での経験の方が圧倒的に多く発信される。
つまり、ここまでの一般的な理由では説明がつかない。
では、なぜ「新幹線だけが話題になる」のか。
考えられるのは以下の2点である。
・④:「快適さへの期待値」が極端に高い
新幹線が他の交通手段と決定的に違うのは、乗客が「快適さ」を当然のように求めている点である。
料金は高く、指定席やグリーン車といったランク分けもある。
多くの人にとって、新幹線は「特別な移動空間」なのだ。
そのため、乗客の心理的な期待値が非常に高く、少しのマナー違反でも強い不快感を抱きやすい。
普段は気にならないような小さな摩擦が、「せっかく高いお金を払っているのに」という意識と結びついて、怒りや不満として表に出やすくなる。
結果として、「新幹線ではマナーが悪い客が多い」という印象が強まっていく。
「快適さへの期待値の高さ」については飛行機についても同じかもしれない。
ただ、飛行機は出発前の手荷物検査、搭乗手続き、出発時刻の数十分前までに到着必須、離着陸時の行動制限など、面倒で煩わしいことがたくさんある。
個人的な意見になるが、長距離であっても新幹線を選択する人は、飛行機を利用する際のこうしたストレスを避けたいという動機があり、より(自分にとって)快適な空間を求めているのかもしれない。
・⑤:多くの人がイメージできて、共感を得やすいように知名度を利用している
もうひとつの大きな理由は、SNSやメディアでの受けを狙るために、新幹線の知名度を利用して、あえて「新幹線で起きたということにして」拡散している可能性である。
迷惑行為の前に「東海道新幹線で」、「のぞみの車内で」という一文を添えれば、誰もが状況を即座にイメージできる。
たとえ、新幹線に乗ったことがない人でも、地元の特急列車をイメージすれば、「そのような場所で起きた出来事」すぐに想像できるだろう。
そうした場所で、「こんな非常識な人がいた」という投稿は共感を呼びやすく、ニュースとしても扱われやすい。
もしこれが、「特急あずさ号で(長野県)松本市の実家へ帰省していたら、隣の客がこんなクズだった!!」と訴えた場合はどうだろうか?
一度も利用したことがない人や、沿線住民以外の人が、列車名を聞いても、「え、何それ?」くらいにしか感じず、身近な出来事と感じない人はきっと少なくないと思われる。
そんな人たちにとっては(たとえ、実際に利用したことは一度もなくても)「新幹線」や「のぞみ」といった名前を出された方がすぐに状況をイメージできるのだ。
ちなみに、2025年現在、あずさ号に使用されているのは、このような電車である。
私は一度利用したことがあるが、車内は日本全国で走っている特急列車と大きく変りはないように感じた。
こっちの方が、新幹線よりも身近な存在で、より感情移入出来そうな気がするので、不思議な話ではあるが…
飛行機は、これまで一度も乗ったことがない人にとっては、どんな場所かを想像し難く、同じ出来事が起きてもイメージが限定的で、話題性が低い。
フェリーや夜行バスのような運賃が安い交通手段を利用した場合は、「お金をケチってそんな安い乗り物を使っているから、値段相応の底辺客と出くわすんだよ(関係者の皆様、無礼な発言をお許しください)」と共感を得られにくい。
このような事情から、「こんなひどい奴に遭遇したから聞いてよ~」と訴えたい時は、「新幹線の車内で起きた」ということしたら、圧倒的に共感を得られやすいと考えられる。
JRにとっては大迷惑な話だけど…
というわけで、私はネットに出回る体験談だけで、「新幹線はこんなに危険な場所だ!!」と主張するつもりはないし、どの交通手段で帰省をするのか、については個人の経験や予算に基づいて、自由に決めたら良いと思っている。
これが私の基本的なスタンスなのだが、一方で「絶対にこれだけは止めた方が良い」と感じる移動手段もある。
次回はその話をしようと思う。