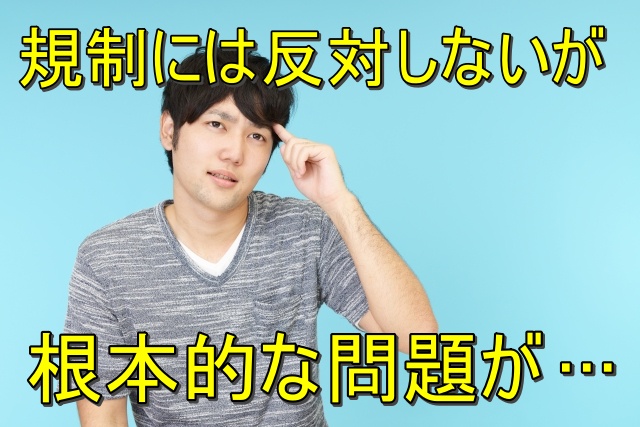
今日は2025年10月1日。
2025年度の下半期が始まるこの日を境に身近な所でもいろいろな変化が起きているかもしれない。
私が注目していたのは、ふるさと納税をめぐる制度改正についてである。
これまで仲介サイトが行ってきた「寄付額に応じたポイント付与」が禁止されるのだ。
ふるさと納税のポイント付与廃止はいつから?いつまでにやるべき?徹底解説! | ふるさと納税サイト「ふるさとプレミアム」
ふるさと納税の目玉といえば、返礼品だと思うが、大手EC(ポータル)サイトでは、数倍ポイント還元といったキャンペーンがたびたび実施されていた。
しかし、総務省は、そうした施策が制度の趣旨を逸脱し、過熱した競争を助長していると判断し、規制を強める方向に舵を切ったのである。
・規制強化の趣旨と背景

そもそもふるさと納税の目的は、都市部に集中する税収を地方へ分散させ、地域の公共サービスや産業振興に役立てることにある。
寄付をした人が翌年の住民税や所得税から控除を受けられるのは、「寄付行為を促すための税制上のインセンティブ」であり、これ自体が十分な見返りであるはず。
だが、実態はどうか。
返礼品競争が激化し、地元産品を名目とした豪華な商品が並ぶ。
さらには仲介サイトがポイントを上乗せし、まるで大型セールのような様相を呈してきた。
総務省もこうした状況を問題視し、2019年には返礼割合を寄付額の3割以内とする上限制を導入した。
ふるさと納税:3割5割は関係ない~2019年度は減少したというのは本当か、その理由は? |ニッセイ基礎研究所
それでも収束せず、今度はポイント施策そのものを禁止するに至った。
背景には、「寄付」という建前と「実質的な購入」という実態との乖離がある。
自治体を応援するという大義名分の裏で、利用者はどれだけ得をできるかに関心を寄せ、自治体もまた多くの寄付を集めるために返礼品やキャンペーンを充実させてきた。
制度が形骸化するのは必然だったと言える。
今回の規制について、私は反対しない。
しかし、こうした規制強化は小手先の対症療法に過ぎない気もする。
そもそも、自治体支援ではなく単なるポイント稼ぎ・買い物化の抑止や、過熱する競争の是正が目的なら、返礼品自体を禁止すべきではないのか?
もしくは、寄付額の3割以内なんて甘っちょろい規制ではなく、5%程度まで抑制して、寄付をした自治体でのみ、もしくはその地域で生産された工芸品・食品の購入のみに限定して利用できる商品券のような「ささやかな謝礼」にとどめるとか。
根本的な問題は、返礼品そのものが制度の方向性を歪めている点にある。
返礼品があるから人は寄付をする、つまり「お得であること」が寄付の最大の動機になってしまっているのだ。
・美しい人と醜い人の差がはっきりと表れる

私は元々、ふるさと納税には一切関心がなかったが、数年前に、とあるECサイトのふるさと納税のページを閲覧しなければならないことがあった。
ふるさと納税を取り扱うECサイトを運営する会社で働くことになったからである。
その時は率直にこんな感想を持った。
「え!? これって、本当にふるさと納税(寄付)のサイトなの!?」
「自分が住んでいる自治体の商品を購入できないこと以外は、普通の通販サイトと全く同じではないのか!?」
トップページにはランキング、セール情報、特集バナー。
カートに入れて決済を進め、後日商品が届く流れは、楽天やAmazonと同じ感覚である。
自治体名よりも、商品や金額をデカデカと全面に打ち出して商品をアピールしているその姿は、寄付が目的のサイトとは到底思えなかった。
こんなサイトを閲覧する人の内、一体何割の人が純粋に「この自治体を応援したい」、「この地域の財源を増やしたい」という気持ちがあるんだろう?
さらに衝撃的だったのは、ポイント還元キャンペーンの日の光景だ。
私の業務上、すべの注文データに目を通す必要があったのだが、ポイント数倍キャンペーンの日には、ポイント目当てのハイエナ共がウジャウジャ湧いてきて、とても「寄付」が目的の人たちには見えなかった。
はっきり言って…
キモ過ぎる!!
魅力的な商品を眺めて、よだれを垂らしながら、「どれにしようかな~」と吟味している人たちは、規制により返礼品が禁止されたら、「じゃあ、寄付なんてしない!!」と被害者意識に満ちて手を引くんでしょうねぇ~
交通インフラ企業の株を大量に取得して、株主総会で配当金や株主優待を目当てに不採算部門の切り捨てを迫る人に対して「社会のインフラを私的な金儲けに利用するな!!」と批判が起こることがあるが、返礼品目当てのふるさと納税は、その最たるものではないのか?
このような欲の皮が千枚頬張った醜い者たちに、本来は寄付が目的のふるさと納税など行う資格はないと言えるだろう。
一方で、災害に見舞われた自治体への支援として、返礼品なしの純粋な寄付をしている人も少なからずいた。
「返礼品!! ポイント!!」という欲望に塗れた拝金主義者たちが溢れる中で、彼らの利他的で思いやりに溢れる姿は何と美しかったことか…
ちなみに、ポイントや返礼品を規制したら、「返礼品があるから寄附するという人が大多数で、禁止すれば寄附総額が激減し、地場産業が衰退する」という批判や反発もある。
私はそのような意見を見聞きすると毎回こんなことを思うのである。
たしかに、金の切れ目が縁の切れ目のような人はいると思うけど…
日本人って、そんなに浅ましい人間だらけなのか?
もし本当なら、同じ日本人として嘆かわしい限りである。
事あるごとに「日本人の民度と気高き精神は世界中から尊敬されている!」みたいな動画やツイートを拡散している人は、こんな予想を立てる人に、さぞかし大激怒していることでしょう。
ちなみ、返礼品制度を擁護する意見には「ふるさと納税のおかげで地場産業が救われている」というものがある。
その説明が私にはどうも腑に落ちない。
2019年の規制により、返礼品は寄付額の3割までに制限された。
仮に10万円寄付したとしても、上限3万円の品しか受け取れない。
残りの7万円以上は自治体の財源とサイトの利用料を徴収している運営者の取り分となる。
制度上は正当な分配とはいえ、数字上は購入者、販売者共に7割の手数料を取られていることになる。
これは事あるごとに「泥棒」だの「奴隷商人」だの罵倒されている人材派遣会社などよりも遥かにひどいピンハネ率ではないのか?
本当に地方の特産品を買いたい、買ってもらいたいのであれば、普通にネット通販をすれば良い。
売り手はまだ地元の自治体の財源が増えることで多少は恩恵があるかもしれないが、買い手は納税も購入も普通にやる方が購入先の自治体を除く多くの人のためになる気がする。
こうして見ると、もはや寄付制度というよりも、自治体が地場産業を利用して、仲介ビジネスをしているようにしか見えない。
悪気がないとしたら、それはそれで輸出国が国内で生産された輸出品に対して関税をかけているようで恐ろしく本末転倒なことをやっているように思える。
善意で無償の寄付を行う人たちもいる中で、今のふるさと納税は本当に「素晴らしい制度」と胸を張って言えるのか甚だ疑問である。









