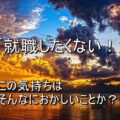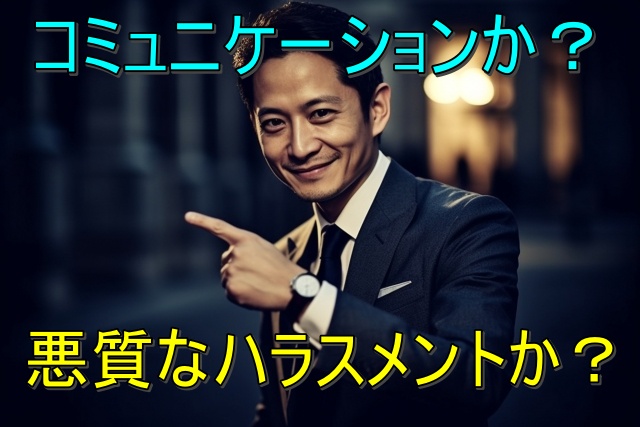
4月1日に新年度が始まり、多くの新社会人が新たな環境でスタートを切った。
希望に満ちた日々を送る一方で、不安や戸惑いを感じている人もいることだろう。
特に、仕事の進め方や業務内容以上に、多くの新入社員が直面するのが「職場の人間関係」である。
上司や先輩との距離感、同僚との付き合い方、上下関係の中でどう振る舞うべきかについては悩みやすい分野でもある。
そっちの方で気疲れして「仕事どころではない」という人もいるかもしれない。
そんな人間関係の中でも、新人が最初に戸惑うことの一つが、勤務終了後に先輩から「飲みに誘われること」への対応だ。
・飲み会の強制参加や断った報復はパワハラだが…

部内全員での飲み会、個人的な誘い問わず、「上司に飲みに誘われたけど、本当は行きたくない」という悩みに直面することは往々にしてある。
さすがに、初回は歓迎会の意味合いもあるため、断る人はそうそういないかもしれない。
だが、問題なのは2回目以降。
「別にどうしても断りたい」というわけでなくても、ここで快諾したら、「喜んで誘いに応じてくれる後輩」だと思われて、その後も毎週(もしかしたら「毎日」かもしれない)のように誘われて、ますます断りづらくなってしまうかもしれない。
ところが、この飲み会問題、実は誘われる方だけでなく、誘う方も悩んでいることが少なくない。
近年では、部下を飲みに誘うことがパワハラと結びつくことも多いため、特に慎重になっている模様。
たしかに、上下関係がある職場において、上司からの誘いを「断りにくい」と感じる部下がいるのは事実である。
そして、もし部下が断っているにもかかわらず、しつこく誘ったり、飲み会への不参加を理由に評価を下げたり、仕事を与えないといった不利益を与えた場合、それは明確にパワハラに該当する。
パワーハラスメントの定義について 平成30年10月17日 雇用環境・均等局
そのことについては、全く異論はない。
しかし、最近ではこうした飲み会の参加の無理強いではなく、単に「上司が部下を飲みに誘うこと自体もパワハラ」という意見も耳にするようになってきた。
たとえ断ることができたとしても、「上司からの誘い」という力関係が存在する以上、「それは『断ることができない空気を利用したハラスメント』である」という主張である。
果たして、それは本当にパワハラに当たるのだろうか?
・嫌なら断ればいい

私はこの考えには強く違和感を覚える。
なぜなら、単純に「嫌なら断ればいい」と思っているからだ。
実際、私は社会人になってからというもの、送別会など今後会うことはないだろう人との最後の機会を除いて、ほとんどの飲み会を断ってきた。
お酒を飲むこと自体が好きではないし、普通の食事であっても、プライベートを優先したいからである。
だが、ここまで「飲み会嫌い」を自認している私でも、飲み会の誘いがあったら(「断るのが面倒だから、そんなもんやるなよ」と思うことはあっても)「ハラスメントを受けた!!」と感じたことも一度もない。
彼らも悪気があってそんな会合を開いているわけではないことは分かっているし、実際に「行きません」と言ったところで、何かしらの不利益を被ったことは一度もない。
陰で「あの人はノリが悪い」とか「付き合いが悪い」と思われたことはあったかもしれないが、そのことによって職場へ行けない程の精神的苦痛を受けたら、そんな会社にはこちらの方から三行半を叩きつける。
最近の風潮では、何か不快に感じたことがあればすぐ「ハラスメントだ」と訴える傾向が強まっているように見受けられる。
しかし、「意に沿わないこと=ハラスメント」という考え方は非常に危険である。
また、武井壮氏の「好みの相手からの誘いには喜んで行くけど、好みじゃない相手からの誘いはパワハラなんだとさ」というXの投稿に対する反応のように、「断ることが難しいからハラスメント」と言いながら、面識もなければ、性犯罪の前科があるわけでもない彼に対して、「このタイプの人って女を見下してて、ご飯食べた後にヤれなかったら逆ギレしてくる人しかいなかった」と暴言を吐く者も現れた。
武井壮が怒り「本当に猛烈に失礼なこと言ってますよ」ハラスメント巡るユーザーの投稿うけ指摘 – 芸能 : 日刊スポーツ
被害者意識には敏感だが、加害者意識に鈍感なのも、すぐに「ハラスメント」と断じる人間の特徴と言える。
もちろん、本当にパワハラを受けている人の声は大切にされるべきである。
ただし、「上司に誘われて嫌だった」という感情だけで、それを即座にパワハラ認定する風潮には疑問を抱かざるを得ない。
というわけで、私は「飲みに誘う=パワハラ」ではないという立場である。
もちろん、根拠は「嫌なら断ればいいから」であるため、この主張に賛成してくれる人は、誘いを断る人を
「付き合いが悪い!!」
「協調性がない!!」
「出世意欲がない!!」
と非難するダブルスタンダードな態度は決して取らないと信じている。