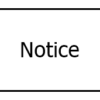・対照的な兄弟
先日、諸事情があり、久々に地元で暮らしている兄弟に電話を掛けることになった。
私は1年以上、地元に帰っておらず、用事がない限り電話もしない生活を送っているため、声を聴くのも1年ぶりだった。
ブログで家族のことに滅多に触れないため、今まで彼のことを詳しく取り上げたことはない。
彼は私より年下だが、結婚していて子どももいる。
そして、地元にマイホームも買っている。
このブログでよく使っている言葉で表現すると、典型的な「安定した生き方」を歩んでいる人間だ。
私が何の当てもなく地元を離れ、ワンルームのボロアパートで暮らしながら、30歳を過ぎても非正規の仕事をする生活を送っていながら、親から一切説教をされないのは、彼の存在によるものが大きいと思っている。
さて、そんな彼に電話を掛けたのだが、私が印象的だったのは、話した内容よりも、電話に入り込んできた生活音だった。
まだ言葉を発することができない小さい子どもの声。
奥様がフライパンで食べ物を炒めているであろう「ジュー」という音。
何というか・・・
いかにも「家族で過ごす夜の時間」という様子だった。
電話越しにそんな音を聞いた私はあることを思い出した。
・家族の帰宅

あれは、上京して3年目を迎える年だった。
派遣の仕事の契約が終了した私は2ヶ月程、次の仕事が見つからず、「さすがにこれ以上、無職生活を続けることはマズいな…」と思って、短期のアルバイトで働くことにした。
その仕事はキャンペーン案内の電話である。
仕事の内容はこの記事に書いた通り、迷惑電話以外の何物でもなく、アポ取りが上手くいかないだけに留まらず、相手から罵倒されることも少なくなかったため、私はかなり精神的に参っていた。
しかも、アポを取ることができなくても、「(潜在的な)お客である子どもの詳しい状況を聞き出せ!!」と指示されていた。
たとえば、「他社の学習システムを利用している」とか「すでに志望校に合格した」など。
もちろん、会員になっているわけでもなく、資料請求しただけの会社に個人情報を漏らすお人好しなどそう多くない。
私はこの仕事が嫌でたまらなかった。
そんな中、珍しく穏やかで紳士的な男性が電話に出た。
彼は私の案内を最後まで聞いてくれた上で、「確かに以前は興味があったが、子どもはまだ小学2年生という遊び盛りの年齢だから、もう少し成長するまで、案内は控えて欲しい」と丁寧に断ってくれた。
それだけでも十分嬉しかったが、私がその時のことを今でも憶えているのは、会話中にこんな音が聞こえたからである。
「ガラガラガラ~」
「ただいま!!」
その日は平日で、時間は夜の8時頃。
恐らく、玄関が引き戸であり、家族が買い物から帰ってきたのだろう。
その瞬間、私は実家のことを思い出した。
・温かい家族への憧れ

家族の誰かが家の扉を開け、「ただいま!!」と言って帰ってくる。
実家に住んでいた時はそんな他愛ない生活音も、平日の夜に家族と共に過ごす時間も、当たり前だったが、その時の私はそんな生活が懐かしく、羨ましささえ感じた。
私は思わず、彼の住所に目を向けた。
県名の後の地名が「郡」になっていたことから、結構田舎の方だったのだろう。
その点も自分の出身地と重ねることになった。
上京して以降、家族の温かさが恋しくなったのはこの時が初めてだった。
安定した仕事が見つからない焦りや不安に加え、客から(迷惑電話なのだから当たり前だが)罵倒されっ放しの仕事で傷ついていた私にとっては、たとえ他人の家であっても、「家族の温かさ」が身に染みた。
そんなこともあったので、当時の私は地元へ帰ることも検討していた。
まあ、ちょうどその頃からコロナの感染拡大が始まり、満員電車が解消され、(過去に比べて少しは)他人への優しさが広がる社会になったことで、その後も東京に留まることになったわけだが。
ちなみに、迷惑電話の仕事は、家族の温かさに触れたことで良心の呵責も生まれ、数日で退職した。
あの日から2年半が経過した先日、再び同じような感覚に襲われた。
始めたばかりの仕事で慣れないことも多々あり、つらい思いをしているという点も同じだ。
すでに退職したとはいえ、前の職場に通っていた時はコロナ渦前を思わせるような通勤ラッシュに悩まされていた。
また、最近は実家に帰っている夢をよく見ている。
それも、単に地元で暮らしているわけではなく、東京の仕事を放棄して実家に逃げ帰る内容であり、目覚めた時には汗をびっしょりとかいていることが珍しくない。
経済的には圧倒的に恵まれているとはいえ、東京の生活はそれだけストレスに満ちているのだろう。
家族も友達もおらず、職場に「仲間」と呼べる同僚がいないことも、ストレスに拍車をかけている。
最近は「いつまでこの生活を続けるのだろう…」と思うことが少なくない。
もっとも、地元に帰ったところで、そのような温かさに迎えられるわけではないが…
だが、ここに来て、家族の温かさに焦がれていることは認めざるを得ない。