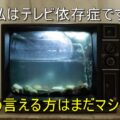前回のテーマは「ある国の人たち」についてだった。
その中で、どうしても書きたかったが、長々と書くと本題から大きく離れてしまうので、外したことが2つある。
今日はそれを前回の補足という形で書いていこうと思う。
・同級生の発言により差別意識に気づく

前回の最後に「その国の出身者の99%が非常識な人であっても、そうではない善良な1%の人が、その国の出身だという理由だけで不当な差別を受けることは許されることではない」と書いた。
それは差別の基本だが、私がそうしないように気を付けているのは、子どもの頃に人権学習で学んだからでも、映画やテレビ番組の影響を受けたからでもない。
きっかけは私が中学生の時の出来事だった。
私が通っていた中学校は公立の学校であり、そこには4つの小学校から進学してくる生徒がいた。
みなさんが中学生の時も同じだったと思うが、入学当初は相手がどこの小学校の出身なのかを意識していても、半年も経てば、そんな壁は崩れたと思う。
しかし、私は、4つある小学校の内の1つの学校(A校とする)の出身者だけは気になって仕方がなかった。
小学生の時に、そのA校ではいじめや不登校者が異常に多いということを聞いていたから。
実際に私が生活していく上で、どうしても関わり合いになりたくないと思った人はA校の出身者であることが多かった。
たとえば、初対面の相手を「オイ」や「お前」と呼び、掃除の時間には人に掃除を押し付けて、自分たちは仲間内で固まり談笑して、バス移動で後部座席を占領してバカ騒ぎするのは大体A校の出身者だった。
もちろん、A校の出身者の全員がそんな感じだったというわけではない。
A校出身者にもまともな人はいた。
しかし、私はA校出身者への偏見を抱き続けた。
それが変わったのは私が中学二年生の時だったと思う。
たしか、翌日が文化祭ということで、2,3人のグループに分かれて、掃除や会場の設置をすることになった。
私は男3人でチームを組むことになった。
仲間の一人はアカダ(仮名)。
彼はA校の出身ではない。
彼と私は一年の時から同じクラスで仲が良かった。
私の先輩はガラの悪い人が多く、体育祭などで関わり合いになる時は、内心、怯えていたのだが、先輩に可愛がられていたアカダと常に一緒に行動することで、やり過ごすことができた。
もう一人の仕事仲間はサトウ(仮名)だった。
彼はどんな人だったのかを説明することが難しいくらい普通の人だった。
強いて言えば、あまり人と喋らないことくらいかな。
ただ彼はA校の出身だった。
私たちの仕事は廊下の窓拭きだった。
途中で洗剤が切れたので、じゃんけんの結果、サトウが用務室へ新しい物を取りに行くことになった。
彼が離れた時にアカダが私に尋ねた。
「サトウ君ってどんな人?実は俺、あの人と話したことがないんだよなあ」
どんな人と言われても、彼は普通の人である。
というよりも、私も彼のことは詳しく知らない。
「僕もあまり喋ったことがないから、よく分からなけど、優しい人だと思う」と答えた後に思わず本音が出てしまった。
「だけど、あの人はA校の出身なんだよなあ」
彼はサトウがA校の出身だと、何かまずいのか私に聞いた。
私は彼に、私が小学生の時に聞いたA校の悪い噂、そして、実際に中学生になってその噂はほぼほぼ本当だと分かったこと、できればA校出身者とは関わり合いになりたくないと思っていることを告げた。
彼もA校出身者に危険人物が多いことは同意したが、その後、次のようなことを言った。
「A校出身者が100人いて、たとえ、その内の99人がヤンキーだとしも、そうではない真面目な1人の人をA校出身というだけで、同じように悪い人と決めつけるのダメだよ」
それを聞いた私はハッとした。
自分が恥ずかしくなり、「自分の考えは間違いだ」と思うようになった。
「A校出身者100人の内99人がヤンキーだとしても」という例えに思わず笑ってしまったが、「そうではない1人を出身校だけで差別してはいけない」ということは全く持って彼の言う通りだった。
私はそれ以来、ヤンキーであることとA校出身であることは分けて考えることにした。
ちなみに、私の考えを正してくれたアカダは、その後、東京の有名な大学に進学した。
学力と倫理に相関関係があるのかは知らないが、私のような凡人とは中学生の時点で大きな差があったのかもしれない。
・人間は自分が気づかないところで輝いている?

前回の中盤に「人は苦しんでいる時に別の世界の人間が輝いている姿を見ると、勇気づけられることがある」と書いた。
だが、輝いている当人はそのことに気づいていないこともある。
これは私が地元に住んでいた時の話である。
当時の私はディスカウントストアで働いていた。
厳密には、私はその店にテナントを出している会社の従業員で、その店の従業員ではないが…(これは後に重要なポイントになる)
販売の仕事なので、売り場で知り合いと出くわすことも珍しくなく、一度、小・中学校の頃の同級生の父親に会ったことがある。
彼は私と顔を合わせるのは今回が初めてだが、彼は今まで何度か私が働いている姿を見ていたと言った。
そんな会話の中で彼の一言が妙に引っかかった。
彼の職業は地元の市役所に勤務する公務員である。
大した産業のない地方に住んでいる人なら分かると思うが、そんな場所で市役所の公務員という身分は特権階級のような羨望の的として扱われる(本当にそんな天国のような職場なのかは一先ず置いておくにしても)。
そんな人が、いい歳して、零細企業のフリーターとして働いている私に、「頑張っている」はともかく、「輝いている」なんて言葉を発したことに、私は妙な居心地の悪さを感じた。
私は「あんた、絶対、家で俺のこと馬鹿にしてるだろ!?」と思いつつ、笑いながら
「冗談はやめてくださいよ」
「市役所で安定した仕事をしている人の方がよっぽど輝いていると思われていますよ」
と返した。
しかし、彼は私の発言をすぐに否定した。
「よく公務員だから羨ましいとか仕事が楽とか言われるけど、こんな仕事をしていると常に組織のことを意識して、自分はその歯車であることを嫌というほど思い知らされる」
「こんな仕事をしていると、本当の自分を見失って、頭がおかしくなりそうになることもある」
彼は特に、毎朝の朝礼で行われる笑顔のトレーニング、ネチネチした正しい敬語やお辞儀の角度の練習が苦痛らしい。
そしてこんなことを言った。
「だから、自分の言葉で喋って、自然な表情で生き生きと働いている君は、いつも輝いて見える。あの時、〇〇(彼の息子で私の元同級生のこと)といつも一緒に遊んでいた君が頑張っている姿を見たら、自分も頑張らなきゃという気持ちになる」
これが彼の本心なのかは分からない。
だが、彼の言う通り、私が働いていた職場は、誰かの顔色を窺ったり、卑屈になることなく自由に働くことができた。
テナントの従業員なので、本店(店を入れているディスカウントストアのこと)のような服装、接客の細かい規定もなく、商品の値引きや配置換えも個人の裁量で自由にできた。
笑顔のトレーニングとか正しい敬語の暗唱を朝礼で行うこともない。
本店の人たちはやっていたが。
悪く言えば貧乏な会社なので、本店と違って、交通費が支給されず、人手も十分ではなかったが、それでも本店の従業員になりたいと思ったことはない。
だって、そこでしか味わえない自由があるから。
彼のような息苦しい職場で働いている人から見たら、たとえ貧乏な会社の単純労働でも、卑屈にならず自由に働いている人は、それだけ眩しく見えるのかもしれない。
私は彼に言われるまで、そんなこと思いもしなかったが、人は自分が気づかない場所で輝いているのかもしれない。