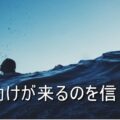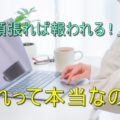前回までのあらすじ
転職することになった私は、転職先の仕事が勤務開始となるまでの間、日雇いの仕事で働くことになった。
その時の体験を基に、前々回は私が働いた現場について、前回は利用した派遣会社について説明してきた。
今日は私が実際に働いた中から、「二度と働きたくない」と感じた仕事を紹介する。
・二度と行きたくない現場=社員がクソな現場

普通ならおすすめの仕事を紹介するところかもしれないが、二度と行きたくないと思った会社のランキングを発表する方がこのブログらしい。
ちなみに、元々は「社員がクソだった職場ランキング」にするつもりだったが、これが見事なまでに「二度と行きたくない会社」と一致していた。(やっぱり仕事で一番大事なのは人間関係ですね)
・二度と行きたくない職場ワースト3位:倉庫でピッキング
「二度と行きたくないと思った職場」のワースト3位は倉庫のピッキング作業である。
(仕事内容についてはこの記事を読んでほしい)
作業が始まると、指導役の社員が端末の扱い方と品物の置き場所、確認するバーコードについて簡単な説明をした。
一通り説明が終わると、彼からこんな質問をされた。
クソ社員:「さて、問題。スキャンするバーコードは何桁だっけ?」
早川:「いや、そこまで詳しくは覚えていません」
クソ社員:「バーコードは11桁って言ったよね?? 君は俺の話を全然聞いてなかったの? それは大問題だよ」
はあ?
バーコードが何種類もあるのならともかく、1種類しかないのに、わざわざ何桁かなんて覚えないし。
また、休憩に入る前にその社員から「休憩から戻っても絶対に自分で端末を起動しないように」と言われていたことがあった。
しかし、午後の仕事時間になっても彼は私の前に現れない。
このままでは仕事ができなくなるので、私は彼を探し回った。
すると、その様子を見ていたお局の風のババアが食いついてきた。
お局ババア:「もう仕事を始める時間なのに、何であんたはそんなにウロウロしているの!!」
早川:「〇〇さん(クソ社員)が来ないから、この端末を起動することができなくて、仕事を始めることができません」
お局ババア:「はあ??」 (←この時の顔はモザイクが必要なくらい酷かった)
ババアはそう言って、私の端末を奪い取り、起動させた後、それを投げるように私に渡した。
というわけで、クソ社員の到着を待たずして午後の仕事を開始することになったのだが、今度は遅れてやって来た彼とひと悶着あった。
クソ社員:「俺、勝手に端末を起動するなって言ったよね? なんで勝手に扱ったの?」
早川:「待っていたら、ババアが起動させて『早く仕事を始めろ!!』と言われました」
クソ社員:「じゃあ、仕方ねえけど、次から絶対に勝手なことはするなよ!!」
勝手も何も、端末を操作して指示を出したのはババアだし…
私がこの瞬間
と思ったのは言うまでもない。
ちなみにこの会社、私が自分の意志でエントリーした職場ではない。
私はこの職場と同じ最寄り駅の配送の仕事に応募したのだが、派遣会社の手違いなのかこの仕事を紹介された。
「今から間違いを指摘しても、どうせ自分がエントリーしたところには紹介されないだろうなあ…」と思って、そのまま就労したのだが、こんなやばい人ばかりいるのなら、やっぱり止めておけばよかった…
・二度と行きたくない職場ワースト2位:配送センターで荷物の仕分け
初回の記事にも書いた通り、この職場で私が担当した業務はコンベアーに流す荷物が積んである台車の取り出しと空になった台車の片付けである。
私は3人の台車を用意するのだが、空になった台車を片づけたり、空になった台車数台を別の場所へ移動していると、彼らは荷物を流し終えてしまうことがある。
そんな時に、エラそうな髭を生やしたオヤジ社員は独り言なのか、私に文句を言っているのか知らないが、わざとらしく「遅えなあ~」と言って、舌打ちをした。
髭オヤジは自分で台車を出すということはなく、腕を組んで、私が持ってくるのをずっと待っていた。
また別の男は自分で台車を用意こそするのだが、空になって台車を私への当てつけのように投げ飛ばしてきた。
ちなみに、荷物を流すコンベアーは私が担当する場所以外にもあるのだが、そこへ持っていく台車が渋滞すると、私が台車を片づけのために通る通路が塞がれてしまう。
そのため、台車を移動させる際に時間がかかってしまうことがある。
そんな時に、例の社員どもは「何で台車を移動させるだけなのにチンタラやってんだ!?」と怒鳴ってくる。
この3人は常に自分たちだけのグループで固まっており、私に対しては文句を言う時しか口を利かない。
初めての仕事で慣れない私を手伝うつもりなど全くない。
そんな時にいつも助けてくれたのが、ベトナム人の青年だった。
彼は上手く日本語を喋ることができなかったようだが、「これ」、「ここ」、「あっち」などの簡単な言葉で指示を与え、手伝ってくれた。
彼を見ていて思ったことがある。
おそらく、私よりも酷い目にあったに違いない。
彼が「これが日本の職場なのだ」と捉えたのであれば、この会社の人間はとんだ国辱ものである。
・二度と行きたくない職場ワースト1位:引っ越し
これらの会社を遥かに凌駕する最低なクズっぷりを見せたのが引っ越しの仕事だった。
集合場所の事務所では担当者が笑顔で出迎えてくれて、休憩室も穏やかな雰囲気だったのだが、思い返せば、これは嵐の前の静けさだった。
客のお宅を訪問すると、まず社員3人が家主に挨拶をしていたので、私たちバイトはその挨拶が終わるのを待っていた。
すると、挨拶を終えて帰ってきた社員の1人が
と怒鳴ってきた。
いや、何から始めればいいか分からんし…
バイトの1人が「何の準備からすればいいのですか?」と質問した。
すると
と言って、結局明確な指示を出すことはなかった。
私は同じ日雇いのバイトと相談して、トラックに積んであったマニュアルを見ながら、運搬用の資材を準備しようとした。
しかし、それらをトラックの外に置く時に使うマットが見当たらない。
そこで仕方なく、空の段ボールを使うことにした。
すると、それを見た別の社員が怒鳴りながらこんなことを言った。
だったら、最初に言えよ。
このバカ!!
ちなみにこの会社の従業員にとって「お前」、「バカ」、「死ね」の3つの言葉は標準語のようである。
バイトの一人がトラックへの搬入中に洋服ダンスを倒してしまい、服が数枚こぼれ落ちた。
その様子を見た社員の1人が、
と言って、物凄い勢いで顔面接近攻撃をしていた。
このような暴言の嵐の中で無事にすべての荷物を積み終わり、トラックで移動となった。
…のだが、ここでドライバーから衝撃的なことを言われた。
何じゃそりゃ??
なぜ日雇いのバイトに道案内をさせようなどと考えるのか?
そんなことして、もし道を間違えたらどうするつもりなのか?
私はとっさに「すいません。自分のスマホは通話専用でインターネットに繋げないんですよ」と言って断った。
ドライバーは一瞬、ムッとした顔で「え!?」と答えたが、これは冗談で、バイトがスマホを持っていないケースも想定しており、カーナビとして使用するタブレットが用意されていた。
ウソを吐いたことで何とかナビ役を押し付けられずに済んだが、もしもこの時に「ネットに繋ぐことできないならどうやって会社に勤怠報告したの?」と聞かれたら一貫の終わりだった。
さて、ドライバーは自分でタブレットを操作してナビを設定したのだが、彼は設定に高速道路の使用を入れ忘れたため、最寄りの高速道路の入り口を通り過ぎてしまった。
それに気づいた彼は勝手な怒りを爆発させ、散々喚き散らしながら、制限速度を超えるスピードで車を飛ばしていた。
危険だし、そもそも後ろには客の家財が積んであるのだが…
私は今後この会社を仕事先としてだけでなく、客としても使うことも絶対にないだろう。
・どんな仕事を避けるべきか?

以上が、私が体験した日雇いで二度と働きたくないと思った職場である。
こうして見ると、二度と行きたくないと思う職場は「仕事がきつい」とか「就業場所が遠いから通うのが大変」ということは一切なく、原因はすべて「人間関係」であることが分かる。
そして、この経験からある仮説を思い浮かべた。
前回の記事で私は「日雇いで労働者を確保しているのは、従業員を常時雇用する体力のない中小企業だ」ということを書いたが、企業が日雇い労働者を求めている要因は他にもあると思う。
それは「労働環境(特に人間関係)が最悪で人が寄り付かないから」である。
そもそも私は日雇い労働とは好ましくはないが絶対悪だとは思わない。
イベントや棚卸といった仕事は特定の日のみ大量の人手が必要であるため、必要な全従業員を常時雇用することは不可能だと思う。
ただし、工場や倉庫の仕事では1日単位で労働者の数を調節する必要があるのかは疑問である。
これらの業種では日雇いではなく、常勤で雇った方がはるかに効率的だし、労働者の側も安定して働くことが可能であれば、それが一番だと考える方が自然だと思う。
にもかかわらず、派遣会社に人材を求めないといけないほど人手が足りないのは、あまりにもひどい職場であるため、退職者が続出しているからなのだろう。
私が働いた工場は運よく、人間関係で苦労することはなかったが、ひょっとすると他の職場は私が経験した倉庫や配送センターと似た状況なのではないだろうか。
これらの業種でまともな職場はそもそも日雇い労働者など必要ないのである。
だから、そのような業種ではハズレの職場を引く確率が高くなるから避けた方が無難である。
段々と話が暗くなってきが、この記事で書いたことはあくまでもこぼれ話程度のことであり、今では笑って振り返ることができる部分が多い。
日雇い労働の本当の悲惨さとしんどさは別のところにある。
次回はその話をしよう。