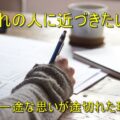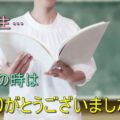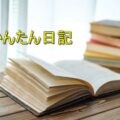今日は久々に英語学習に関する記事を書こうと思う。
英語学習がテーマとなるのは昨年の8月以来だから、およそ半年間ご無沙汰だったことになるが、これには理由がある。
昨年の9月から12月にかけて、勤務先から時差出勤を要求されたため、勤務時間が通常よりも1時間後ろにずれ込んだ。
そのため、平日に帰宅するのは午後8時過ぎとなっていた。
そこから、夜の運動や入浴、夕食を行うと時間はあっという間に9時になる。
さらに、その時期はブログの投稿数が増えたため、帰宅後や週末はブログ作成や読書に多くの時間を費やすことになった。
その結果、それまでの日課だった英語学習が完全にストップし、通勤時間や仕事の休憩中に単語の復習をすることくらいしかできなかった。
そんな生活を数ヶ月送っていたが、今月に入り、その時差出勤が解消されたことで、英語学習を再開することにした。
・あれもこれも教の襲来

再開に備えて、何冊か本を購入した。
その一冊がビジネスメールの表現に関する本である。
その本は最初に日本語のビジネスメールを読んで、それを英語に訳していく形式を取っている。
最初は順調だったが、次第に雲行きが怪しくなってきた。
あ、これはさっき出てきた
に違いない。
さて、正解は…
あれ。
これはまさか…
一抹の不安を抱えながら、私は先に進めた。
あ、これもさっき出てきたやつだ。
さて、答えは…
来たぁぁぁ!!
これはまさしく英語学習の天敵である「あれもこれも教」ではないか。
「あれもこれも教」について簡単におさらいしよう。
スティーブ・ソレイシイという人が英会話の本で、面白いたとえ話をしていた。
日本人はネイティブよりいろいろな英語の知識を知っているのにベーシックな会話能力がない。これはスゴクかわいそうなことだ。
まるで、大工さんが1万個の細かい道具をそろえたけれど、道具が重たくて建設現場にたどり着くことができないのと同じだ。たとえ、うまく建設現場にたどりつくことができたとしても、道具箱からいったいどれを取り出して、どう使えばいいのかがわからないほど、道具が雑然としている。
このような状態を解消するために、似たような表現をいくつも覚えるのではなく、最初は、数は少なくてもいいので、汎用性の高いフレーズを覚えて、これの言葉がすぐに出てくるまで何度も反復する。
そして、そのフレーズを応用することで徐々に使える表現を増やしていく。
これが彼の考える、基礎から固める英語勉強法である。
一方で、同じ「基礎を固める」という言葉を使っている人でも全く正反対のことを考えている人も少なからずいる。
それは、「あれも、これも」と言って、いくつもの表現を詰め込むことが第一だと考える詰込み型信者たちである。
彼らはたとえ使えこなせなくとも、とにかくいくつもの表現を覚えることが「高い基礎能力」だと信じて疑わないが、反復練習を軽視しているため、どこが「基礎を大事にしていると言えるのか?」は私には疑問である。
そして、他人の些細な間違いに対しては「基礎をおろそかにするからだ!!」とイナゴのように湧いてきて嬉しそうな顔で批判する。
・ビジネスシーンでは日本語でも同じ言葉の繰り返しである

さて、あれもこれも教の主張にこのようなものがある。
なるほど。
趣味で行う英会話ならまだしも、ビジネスの場面では相手にそのような印象を持たれることはマイナスであり、その主張は一定の妥当性がありそうである。
だが、私はビジネス英語を使う時ほど逆に厳選したフレーズを繰り返し使うべきだと思っている。
考えてみてほしい。
ビジネスのシーンでは初対面の相手にもかかわらず
と、相手が二度と連絡をしてくることはないと分かっていても
というような心にもない常套句がすぐさま口に出てくる。
このようなフレーズを口に出す時は、「確かこの場面は…」というように、いちいち何か考えて発言しているのだろうか?
ほとんど人(というよりも全員)は、ストックしてあるフレーズが自動的に出てきて、「たまには別の言い方をしてみよう」などとは考えもしないだろう。
メールのテンプレートなどその典型である。
あらかじめストックしている定型文から、適当なものをコピペしているが、同じ表現を無駄にいくつも保管したり、使い分けたりすることなど全くない。
・読者のことを考えているのか?

ここで著者(及び、制作に携わった人)に問いたい。
「その詰込みは本当に必要ですか?」
もしかしたら、「一冊の本になるべく多くの情報を詰め込んだ方が、お得感が出て、読者も喜ぶのでは?」という善意に基づいて作っているのかもしれない。
しかし、以前書いた通り、コストパフォーマンスが優れている本が良書であるとは限らない。
また、「ビジネス英語」と聞くと「それなりに能力がある人が使うもの」というイメージがあるため、「一生懸命覚えるぞ!!」と高いモチベーションを持っている読者を想像しているのかもしれない。
しかし、「仕事で使う」と言っても、それは「使わなければならない」の意味に近く、むしろ嫌々覚えている人が大半なのではないか?
高い給料をもらっていたり、社会的な地位の高い人たちは、「常にやる気に満ちて、より高みを目指そうと努力を惜しまない」と想定することは間違いである。
かくいう私も以前は「大企業の総合職で働いている人たちは(ほぼ)全員が昇進することに命を懸けている」などというステレオタイプな偏見に満ちていたが、実際に同じ職場で働いていると「他人を蹴落としてでも、のし上がるぞ!!」などという野心は持っている人など全くいなかった。(その時の記事はこちら)
と考えるのは見当外れであり、下手したら、外国人の恋人がいたり、外国の映画やドラマに夢中になっている人の方が、よっぽどやる気があるように思える。
なお、この傾向は英語以外の語学にも見られるようである。
昨年、中国語を学んでいる同僚の話をした。
彼も私と同じ意見であり、自分の体験を話してくれた。
初心者向けの日→中の練習本で「テレビを買った」とすればいいものを「プラズマテレビを買った」というように日常会話で使う機会が多いとは思えない単語をわざわざ使用していることがあったという。
その他にも、「~へ行った」と言う際の地名に、北京や上海などではないマイナーな地名が数多く登場してきたらしい。
彼は賢い人だから、そのような単語が出てくる問題は無視して進めていたらしいが、著者は読者がそのような(必要もない)壁にぶち当たって勉強を辞めてしまうかもしれないということを想像できなかったのだろうか?
あえて壁を高くすることで、「それを乗り越えてほしい」とでも言いたいのかもしれないが、
それはあんた一人の自己満足だろうが!?
と言いたくなる。
「あれもこれも教」は学習者をおざなりする著者の独りよがりな気がしてならない。