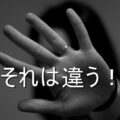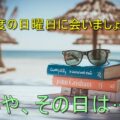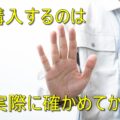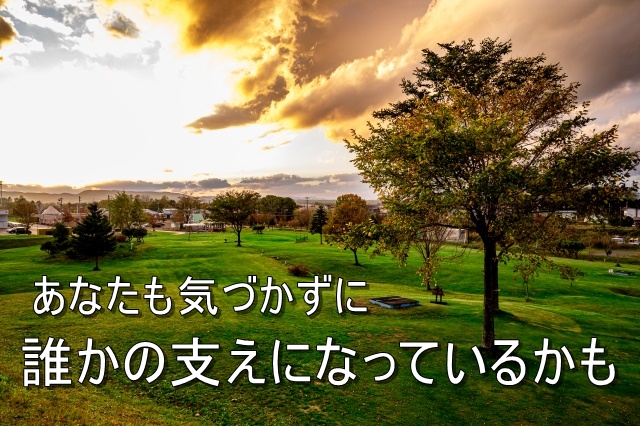
一人で長い時間を過ごしていると、ついついこんなことを思ってしまう。
「心の支えが欲しい」
そんな思いから、恋人や結婚を望む人もいるが、この悩みは独身者だけでなく、家族やパートナーがいる人であっても感じることがある。
今日はその「心の(精神的な)支えとは何か?」について考えてみたい。
・私と地元の友人は腐れ縁なのか?

今回、私がこのテーマを取り上げることになったきっかけは、1ヶ月ほど前に前回の記事の構成を練っていた時に、地元の友人であるマサル(仮名)のことを考えていたことから生まれた。
私が地元へ帰省する時は必ず、精神疾患を抱えて一時期(といっても6年の長期だったが)音信不通になっていた彼と会っている。
このことを人に話すと驚かれることが少なくない。
その理由は私と彼の間柄にあるらしい。
進学や就職で地元を離れた後も、かつての友人たちと連絡を取り合い、地元に帰る度に再会することはそこまで珍しくない。
しかし、そのような関係が築ける元同級生とは、大半が高校や大学時代の友人である。
マサルと私は小・中学校の同級生だが、高校は別の学校へ進学した。
そのような間柄で、大人になっても付き合いを続けることはかなり珍しいそうだ。
そういえば、この記事で少し触れた、かつて高校を中退しようとして担任の教師から説得された時にもこんなことを言われた。
「中学の時までの友人は大人になると付き合いが消滅する」
これは少なくない人の間では常識になっているのかもしれない。
それから、彼と私は離れて暮らしているだけでなく、日常的に電話やメールのやり取りを行っているわけでもない。
彼は精神を病んで以降、携帯もパソコンも使えなくなった。
そのため、離れていても毎日のようにSNSで連絡を取り合うことはできない。
だからこそ、私が地元に帰省する時は直接会って話をするわけだが、その関係は人によってはとても不思議に映るらしい。
いくら長年の関係があると言っても、普段は全く連絡を取り合っていない相手と話ができることは有り触れた関係ではないようである。
昨年のゴールデンウィークに帰郷した際に彼と会おうとして、彼の実家へ連絡したら母親からこんなことを言われた。
私はそれでも構わなかった。
他に親しい友人も恋人もおらず、同僚にも心を開かず、家族にも仕事の話をしない猜疑心の塊のような私にとって、彼は長年の付き合いがあり、素面で接することができる数少ない人物である。
たとえ、以前のような関係に戻れずとも、失った空白の時間も戻らずとも、彼と会って話ができればそれで十分満足なのである。
「腐れ縁」と言えばそこまでだが、このように経済的な利害関係もなければ、同じ場所で同じ時間を共有している地縁もなく、その上、6年以上の空白があったとしても、引き寄せられる関係とは一体どんなつながりだと言えるのだろうか?
・愛着とは片思いでも構わない

そんなことを考えていた時に「愛着理論」というものを知った。
愛着の主要な目的は、愛着の対象となる養育者から、探索の基地となる安全地帯と不安を避ける安息所を提供されることである。
小さな子どもを例にして考えてみよう。
質の良い安全地帯を持つと子どもは安心して周囲を探索することができる。
安全地帯があれば安心して子どもは探索行動に夢中になり、めったに愛着行動を見せない。
愛着の対象が自分の冒険を見守ってくれ、喜んでいてくれることを期待し、また、必要な時には頼みにできると信じているからである。
不安やストレスが起こる状況になって自分ひとりでは処理できなくなると、愛着の対象に保護や援助を求めにやってきて安息所を得る。
これは幼児の例であるが、年長の子どもでも、大人でも、愛着が安心・安全をもたらす仕組みは同じである。
年長の子どもは愛着の対象に抱っこされなくても優しい言葉をかけてもらうだけでよいかもしれないし、成人なら心の中にこのような仕組みがあれば、その人を思い出したり、その人ならきっと支持してくれると考えて安心できるだろう。
つまり、愛着は「心の居場所」を提供する。
ここで重要なのは、愛着を向けられた相手がこれに応えてくれることやポジティブな感情を持つことは、愛情の定義には含まれないことである。
愛着は一方向的なもので、絆や母子関係、人間関係のように双方向的な関係ではない。
このような愛着による「心の拠り所」が「心の支え」という意味なのだと思う。
私がマサルに抱いている感情はこれに似ていると感じた。
前回の記事で紹介した通り、私の子どもの時の夢は仕事で自己実現することではなく、地元の仲間たちといつまでも笑って暮らすことだった。
だからこそ、彼ら友人たちと連絡も途絶えてしまった時は、ただ単に距離が離れてしまっただけでなく、彼らが本当に私の世界からいなくなった気がして、目の前が真っ暗になった。
これが「心の拠り所を失う」ということだろうか。
その上、仕事の面でも壁にぶち当たった私は、この社会で生きることさえも絶望した。
このようなことがあったからこそ、彼の状態がどうであれ、再会できた時はとても嬉しかった。
・「離れていても心は繋がっている」の意味
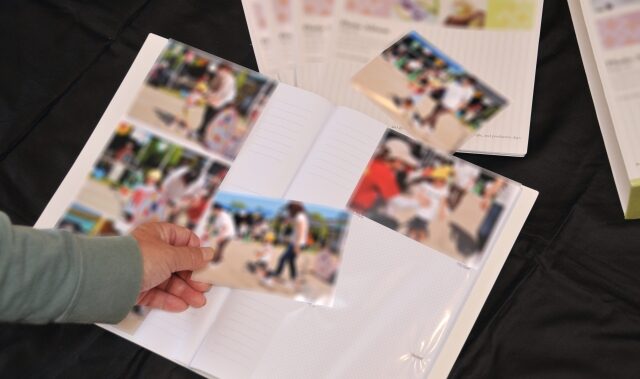
私が地元へ帰るのは多くても半年に1度で、1年以上戻らない時もある。
それに加え、スマホもパソコンも持っていないマサルとは離れていても連絡を取ることはできない。
それを考えると、実際に彼とコミュニケーションを取る頻度は空白だった6年間と大きな違いはない。
しかし、精神的な安定度は全然違う。
隣にいられなくても、連絡を取り合うことができなくても、「彼が今も友達である」という思いだけで、私の心は支えられている。
このように、愛着の対象から具体的なサポートを得られなくても、心の支えを得ることはできる。
つまり、心の支えを得るためには、家族や異性と結ばれる恋愛関係のような特別な間柄にならなくても、「あの人は自分の味方でいてくれる」という一方的な好意だけで十分なのである。
「離れていても心は繋がっている」という言葉がある。
この言葉は決して、離れて住んでいる相手と毎日のように電話やネットで長時間のやりとりをする意味ではなく、このような「隣にいなくても、あの人は自分の味方でいてくれる(はず)」という信頼から生まれるものなのだと思う。
親が離れて暮らしている子どものことを思う時に、たとえ子どもから金銭的な援助を受けなくても、子どもが元気に生活している様子を知るだけで、生きがいを感じることがあるのも同じ理屈だろう。
思い返せば、共にこのブログを運営するはずだった幻の相方(某国のバックラー)が言っていた「苦しい生活を送っている人たちが、仲間が外国で生き生きと生活している記事を読んで生きる希望が生まれる」ということも、その記事で紹介した「学校で辛い体験をしている子どもが、テレビの中で輝いている芸能人やスポーツ選手を見て勇気づけられる」ことも同じことなのかもしれない。
このようなケースは、相手が直接自分へメッセージを送ってくれることも、生活の支援をしてくれることもなく、一方的に感情移入するだけだが、それでも、その存在自体が心を支えてくれる。
宗教に支えられる人も同じだろう。
公的な社会保障の存在しない国では宗教共同体がセーフティーネットとなっているため、経済的な結びつきが全くないとは言えないが、宗教における信仰とは見返りを求めず一方的に神を崇めることが基本である。
他人から見れば、「この人は何でこんなことを大事にしているのか?」と思われても、彼らの心はその「神」の存在によって支えられているのである。
・今日の推薦本
高橋惠子(著)講談社現代新書
「愛着理論」の参考に使用した本。なお、著者は愛着理論については一定の評価をしているものの、提唱者であるジョン・ボウルビィがこの理論を母子関係のみに適用しようとしている点については批判的である。