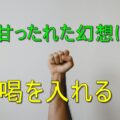これは2週間ほど前のできごとである。
私は先月配属されたばかりの新入社員に道案内を兼ねて、一緒に郵便局へ行くことになった。
時間は2時を過ぎた頃だった。
その日は晴れで、ちょうどその時間帯が最も暑かったと思う。
郵便局へ向かう途中に交差点があり、そこで信号待ちをしていると、一瞬小風が吹いた。
その交差点は狭い小道の上り坂を進んだ先にある。
交差点の手前には古めかしい個人商店があり、店先には懐かしいデザインの飲料水が並べられていた。
そんな場所で、ガンガン日に照らされて、小風に枝を揺らされて音を立てている木々を見ていると、東京の中心部にいるのだが、まるで地元の田舎にいるかのような錯覚に襲われた。
私は同僚(新入社員)に声をかけられるまで、信号が変わったことに気付かなかった。
私は職場ではほとんど表情を変えず、同僚と世間話に花を咲かせることもない。
彼はそんな私が信号が変わったことにも気付かないほど上の空になっていたことを心配してくれたのか、「何か考え事でもしていたのですか?」と尋ねた。
特に事情を隠す理由もなかったため、私は彼に地元を思い出したことを打ち明けた。
・あの夏の思い出

私は夏が好きというわけではない。
冬の寒さは嫌いだが、夏の暑さも同様に鬱陶しく感じる。
「日本は四季があるから素晴らしい!!」などとほざいているバカを見ていると本当に腹が立つ。
しかし、どういうわけだか知らないが、夏は完全に切り捨てることができない。
それは、今でも記憶に残っている思い出の多くが夏に経験したことであるからであろうか…
学生の時は夏休みという大きなイベントがあるため、その期間に思い出作りをする機会が多いのは当たり前かもしれないが、学校を卒業してからも思い出は夏であることが多い。
高校卒業後に都会へ進学したものの、挫折して地元へ戻ってきた友達と当てもなく街中を歩き回りながら、学生時代や将来のことを語り合ったこと。
免許を取ったばかりの友達(先ほどの友達とは別の人)の運転する車に乗って、彼の祖母の自宅へ行き、アイスをご馳走になったり、川で遊んだりしたこと。
学生時代は一度も出かけたことがなかったが、彼らと一緒に祭りや花火大会へ行ったこと。
彼らが就職して疎遠になった後も、以前のような関係に戻れることを信じて、よく彼らと一緒に遊んだ場所へ一人で赴いたこと。
都会の大学へ進学した身内が卒業後に実家へ戻ってきて、よく一緒にドライブへ出かけたこと。
こんな話をすると、彼は「失礼かもしれませんが…」と前置きしたうえで、「いかにも田舎の思い出って感じですね!!」と答えた。
ちなみに彼は生まれも、育ちも、現在の住まいも一貫して東京23区である。
私はその場所を直接訪れたことはないが、電車に乗って沿線を眺めていると、いかにも都会の住宅地という印象がある。
田舎の生活などメディアを通してしか目にすることのなかったであろう彼は、私の話を聞いて「僕もそんな生活を送ってみたかったです」と言った。
・戻るつもりはない

同僚の彼は私にこんなことを尋ねた。
「地元に居た時は充実した生活を送っていたようですけど、今からでも地元に戻るという考えはないのですか?」
私はその問に「それはない」と即答した。
私は知っている。
今から地元に戻ったところで、このような思い出に満ちた生活を生き直すことなどできないことを。
あの時、共に楽しい思い出を作った友達も、一緒に住んでいた身内も今は地元にいない。
精神疾患を起こして実家で療養している一人を除いて、全員都会へ働きに出た。
私の地元には満足に生計を立てられるだけの仕事などほとんどない。
ちなみに低収入なだけであればマシである。
低収入であっても「正社員だから」という理由で会社から無制限の拘束を受けるし、非正規という働き方を容認する土壌もない。
実際に私たちがのんびりした田舎の生活を謳歌できたのは、生活の基盤を親に頼れていたからである。
その支えを失ってしまえば、一気に転落するだけである。
また、雇用先は年功序列も終身雇用も存在しない会社が大半であるが、人々は日本型雇用の幻想を追い求め、それこそが唯一絶対の安定の源だと信じて疑わない。
そして、その希望がかなわない現実に苛立ちを募らせる。
そんな「安定」なんてものが、本当に実在したかどうかは疑わしいが…
私はそのような非現実的な生き方を求める圧力に愛想を尽かして東京へ出ることにした。
・異なる地元への想い

さて、何の因果が知らないが、私の所属する部署の部長は私と同郷である。
彼は育ちも就職もずっと地元だったが、3年前に単身赴任で東京へやって来た。
普段は私と違うフロアで仕事をしているため、毎日顔を合わせているわけではないが、私に会うたびに地元の話をする。
彼は生まれ育って、今も家族が住んでいる故郷を愛しているのだろう。
そんな理由からなのか、出身地が同じ私のことを気にかけてくれているのかもしれない。
彼は地元に残った家族や故郷への思いがあり、経済的にも心理的にもつながっている。
彼が東京で働くことで家族は今の生活が成り立っている。
いつかはそこに帰れると信じているからこそ、地元からも家族からも遠く離れた東京での生活に耐えられるのだろう。
このような人は「地元への思いが都会の生活を生き抜く糧」になっていると言えるのかもしれない。
しかし、彼と私は根本的に違う。
彼は自分の意志ではなく会社の人事異動で地元を離れたが、私は三行半を叩きつけるも同然に自分の意志で離れた。
彼は東京で懸命働くことが地元で暮らす家族のためになるが、私はいくら東京で懸命に働いたところで地元とは経済的にも心理的にもつながることはない。
私と彼は出身地が同じだが、地元への思いが全く異なる。
彼にとって地元とは「帰るべき場所」であり、その思いが日々の生活の糧になっているが、私にとっては「帰るべき場所」ではない。
・消えない記憶

私が地元で恵まれた生活を送れたことは事実だが、今から地元に戻ったところで昔のような生活には戻れない。
私にとって地元とは、ありもしない正社員型の安定幻想に縋って、朽ち果てていくだけの瀕死の病人のようなものである。
そんなところに戻ったところでまともな生活など送れるわけがない。
そこはもはや「帰るべき場所」ではないし、地元への愛着など口にすべきではない。
東京へ出て来る時はそう覚悟していた。
…はずだったが、
どういうわけだか、未だにかつての地元での生活が忘れられない。
東京へ出てきて数年が経過するが、「東京の生活って楽しい!!」などと感じたことなど一度もない。
「東京に出てきてどこか面白い場所は見つけた?」と聞かれて返答に困るほど、どこかに出かけた記憶もない。
現在の居住エリアにどんな飲食店があるのかも知らない。
このように、都会らしい生活の楽しみを経験したこともない。
というよりも意図的に避けてきた気がする。
地元に帰っても、以前と同じ生活が送れることはできないと何度も自分に言い聞かせてきた。
しかし、当時の記憶が表象となり、「あの時のような生活に戻れるかも」というわずかな希望が生まれ、東京の生活に適応することを阻んでいるのかもしれない。
ただし、それは部長のような、心を支えてくれる「現実の地元」ではなく、「地元の幻想」に過ぎない。
だとしたら、私の心は幻によって支えられていることになる。
何と虚しいことか…
そんな幻想に未練を持つことなどどう考えても間違っている。
・幻想は心の中にひっそりと閉まっておこう

…と考えていたが、一緒に郵便局へ行った同僚の言葉を聞いて、それが良いことなのか悪いことなのかが分からなくなった。
なるほど。
彼のようにずっと東京で暮らしている人は都会の生活が世界のすべて(「世界」が大げさなら「日本」)であり、他の世界を知らない。
そのため、その生活に適応できないことは「適応できない自分が悪い」「この世界では生きていけない」という深刻な自責の念に直結する。
一方の私は、たとえ幻だろうが、別の世界を知っている。
だから、東京の生活に殺されると感じるのであれば、すぐに逃げ出すことができる。
実際に東京へ出てきてからも順風満帆だったというわけではない。
それでも、「自分が悪い」などと思って、自分に絶望したことはなかった。
そう考えると私は故郷の幻想に守られて生きてきたのかもしれない。
ただし、幻想は幻想である。
自分の心を支えるためにはどんな幻想に縋ろうとも自由だが、それを現実と混同して、他人に強要すれば、それは自称社会人や、地元で就職・結婚することをしつこくすすめる元同僚と同じになる。
故郷の幻想は自分の心の中に閉まっておいて、つらい時にひっそりと思い出すものだという程度に留めておこう。
なお、今回登場した新入社員と私の詳しい関係について知りたい方はこちらの記事をご覧いただきたい。