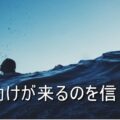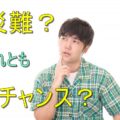2週間前に書いた記事で、私が新入社員と一緒に郵便局へ出かけた話をした。
彼と私は席が隣同士ということもあり、あの一件以来、休憩時間に雑談をすることも増えた。
彼は「同期の仲間」の話をすることが多い。
他所の部署、店舗に配属された同期とお互いの職場についての意見交換をしているとか、同期で飲み会に行きたいけど、(緊急事態宣言が解除されたとはいえ)まだまだ難しそうであるとか。
同期の絆とは特別なものであり、たとえ、毎日顔を合わせることができなくても、同じ立場の人が頑張っていることを思うと、「自分も頑張らなくては」と励みになる。
…らしいのだが、彼の話を聞いていると時折疑問に思うことがある。
その疑問とは
・勤続年数の序列は鉄の掟?

私は彼にその疑問を尋ねることにした。
彼の意見としては
「『同期』とは同じ年齢の人ではなく、入社時期が同じ人のことを指す」
らしい。
彼は97年度生まれで、今年の春に22歳で大学を卒業した。
もしも、大卒までに1年浪人している同期入社の人がいると、年齢では彼の1つ上になるが、彼はその人も「同期」だと思っている。
ちなみに、私たちの勤務先は高卒の新卒者も採用している。
もしも、彼と同じ97年度生まれの人が高卒で入社した場合は、今年で5年目を迎えることになる。
というわけで、人事異動で、彼の所属する部署に同じ年齢で高卒5年目の社員がやって来たとしよう。
すると、彼は「自分の『同期』が来た!!」という気持ちになるのだろうか?
彼の答えは「否」だった。
たとえ、年齢が同じでも、すでに入社して5年目を迎える社員のことは「先輩」と考えて、もし、一緒に仕事をすることになっても、「同期」とみなすことは出来ず、敬語で接するだろうと考えている。
私はさらに意地悪な質問を続ける。
高卒と大卒では昇進のスピードが違うことが珍しくない。
ということは、大卒の彼は、たとえ入社時期が遅くても、高卒の同年齢の人よりも早く昇進して、直接の上司になる可能性が高い。
もしも、そのような状況になると、ある日を境に、彼は勤続年数が長く自分の「先輩」だと思っていた同年齢の社員の上司になってしまう。
そうした場合は、これまでの「先輩ー後輩」としての立場を忘れて、上司として命令口調で接するつもりだろうか?
組織の序列に忠実であるならば、おそらくそうなるだろう。
しかし、彼の答えはまたしても「否」だった。
たとえ、上司となり、これまでの「先輩」を監督する必要があっても、そんな態度で接することはできない。
それが、彼の考えである。
彼の意見をまとめるとこうなる。
・入社時期>役職≧年齢
彼にとって「同期」とは入社時期のことであり、「年齢」は大して重要ではない。
そして、それは時に役職をも超える力を持つことになる。
勤続年数や入社時期を基準にした「同期の力」とはここまで強力なものなのかと改めて思い知った。
(実際のところ、それではスムーズな組織運営が行えないため、大企業では、そのようなことが起こらないよう人員を配置するらしいが…)
・私には「同期」などいない

さて、私がここまでしつこく彼に「同期とは何か?」を問いただした理由は、私がこれまで仕事をした中で「同期の存在」なるものを感じたことが一度もないからである。
学卒時に大企業のような数十、数百人単位で新卒者を雇うような会社に就職したわけでもなく、短期派遣の大量募集のような特殊な案件を除いて、「誰かと同じ日に入社する」という経験すらない。
私はこの記事にも書いた通り、勤続年数よりも年齢を基準に判断していた。
役職がある場合はともかく、同じ立場で仕事をしているのなら、私よりも後に入社した人でも、年上の相手には敬語で接してきたし、自分が彼らの先輩だと思ったことは一度もない。
「何歳ならこうあるべき!!」などと考えて、何に対しても「年齢!! 年齢!!」としつこくやり玉にあげる風潮は間違いだと思うが、それでも年上の人に対しては節度をわきまえて接してきたつもりである。
というわけで、私にとって「同期」とは「同じ時期に入社した仲間」ではなく、「自分と同じ年齢の仲間」に近いのかもしれない。
とはいっても、私が実際に同じ年齢の人と一緒に働いたのは20代後半の時が初めてであり、それまでは「同期」と思えるような人などいなかった。(しかも、その時はいろいろあって同じ歳の人に仲間意識を持つことさえ自重していた。詳しく知りたい方は関連記事を読んでもらいたい)
果たして「同期」とは「同じ年齢の人」に対して使う言葉なのか?
それとも、「同じ時期に入社した人」のことを指すのか?
「そんなの個人の価値観によるんじゃねえ?」
そう返されたら、そこまでの話であるが、私はこの違いは個人の価値観よりも、雇用形態によって生まれるのではないかと思う。
・雇用形態の違いが生む「同期」の違い

前回の記事で「メンバーシップ型」と「ジョブ型」という2つの雇用形態について説明した。
「メンバーシップ型」とは候補者が「どんな仕事ができるのか?」は大した問題ではなく、先ず人柄や潜在能力などの「人」を見て雇い入れるかを判断して、どんな仕事をさせるのかは入社後に決定する。
そして、入社後は「仕事に従事する」というよりも「企業の構成員として振る舞う」ことが重要で、その会社の従業員である限り、どの部署でどんな仕事をしているかに関係なく、「同じ会社のメンバー(仲間)である」とみなされる。
「日本的」と呼ばれることの多い「新卒一括採用」「長期雇用」「年功序列」とはこのメンバーシップ型雇用の考えに基づくものである。
一方で、「ジョブ型」とはその職務に従事する人間が必要になった時に、適任な人物を採用する。
あくまでも「仕事」がベースにあるため、自分の任された仕事以外をする必要はないが、担当している仕事が消滅したら、雇用関係は解消され、労働者はその職場を去らなければならない。
このような雇用形態は欠員が出た時に求人を出す、通年採用が基本であり、経験のない新卒者が一括採用で大量に採用されるということはない。
諸外国ではこのような雇用形態が一般的だと言われている。
ここで、最初にした同僚の話に戻りたい。
現在、私たちが働いている職場は大企業であり、派遣社員の私は「契約の切れ目が縁の切れ目」であるジョブ型雇用に従事しているものの、正社員の彼はメンバーシップ型雇用に身を置いている。
メンバーシップ型雇用では新卒一括で採用するため、同じ日に入社する仲間が数十人(場合によっては数百人)いる。
長期雇用が前提の年功序列であるため、入社時期が同じなら、これから先も(その時々で就く業務は違えど)同じようなキャリアを歩むことになる。
そのため、入社時期が同じ人のことを「自分と同じ存在=同期」だと思うことができる。
余談だが、1,2歳の差なら入社時期が同じなら「同期」と考えている彼でも、同じ2020年入社の中途採用者は「同期」とみなしていない。
年齢があまりにも離れているということもあるだろうが、彼ら新卒者とはキャリアコースが全く違うことを事前に認識しているから「自分と同じ」とは思えないのかもしれない。
一方で、ジョブ型雇用の場合は欠員補充が原則であるため、誰かと同じ日に働き始めるということ自体が滅多にない。
仮にあったとしても長期雇用が前提ではないため、数十年も同じ会社で共に働き長期的な関係を築くなどということはあり得ない。
そして、担当する職務が異なれば、二度と顔を合わせる機会がない可能性もあり得る。
そのような働き方をしていては、入社時期だけを根拠にしても、「この人は自分と同じ=同期」だと思うことはできない。
そんな人たちが「この人は自分と同じだ」と感じることができる共通点が「同じ年齢」なのである。
1年が過ぎれば年齢は変化するが、「自分と同年齢である」という事実は不変である。
だから、ジョブ型雇用のように、立場や職務や勤続年数に幅がある人の集まる集団でも「決して変わらないもの」として安心して心の拠り所にすることができる。
以前の記事で、同じ時期に入社した人たちではなく、数ヶ月後に入社した同年齢の私に仲間意識を感じていた元同僚の話をしたことがある。
思い返してみると、彼女と一緒に働いたのは新卒者など採用しない外資系の企業であり、勤続年数に比例したキャリアコースなど存在しないジョブ型雇用の会社だった。(退職日にメンバーシップ型雇用の良さもあることも知ったが)
そのため、彼女が職場に同じ年齢の人がいないことに不安を感じたり、入社時期が違っても同じ年齢である私に親近感を持っていたことは自然なことだったのかもしれない。
このように「同期」という考え方は、個人の価値観よりも働いている環境によって左右されるものなのだと思う。